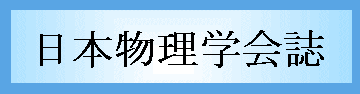
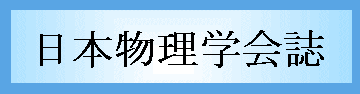
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。 ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
短評
パリティ編集委員会編色とにおいの科学
丸善、東京、2001, viii+152 p., 19×13 cm, 本体1,800円(パリティブックス)
仁藤 修〈東京農工大工〉
電磁波、可視光というと我々にとって身近な対象であり、その波長やスペクトルについて容易に説明できる。ところがなぜその光が色づいて見えるのかというと考えてみたことはあまりない。ましてなぜにおいを感じるかというと答えに窮する人も多いのではなかろうか。物理計測機器についてその原理から説明できても、視覚、嗅覚、味覚といった知覚の仕組みについてはうまく説明できない。本書は物理科学雑誌「パリティ」誌の記事の中から6人の著者による色に関する記事を4編、においおよび味覚に関する記事を2編取り上げて再編集したものである。「色とは何か」「ものが見えるとはどういうことか」「味覚と嗅覚の物理」などからなる。ニュートンによる色の研究の歴史から、分子レベルで網膜中の4種の視物質の刺激から始まる色を感じる仕組み、化学物質が嗅細胞や味細胞を刺激することから感覚を生じる嗅覚、味覚についてまで、興味深く読むことができる。各内容は時間をおいてそれぞれの専門家によって別々に書かれたもので、一部加筆されているが、最新の研究、知覚センサーの開発などには記事のその後もあるように思う。また専門用語や化学分子名が出てきて専門外の読者には取っつきにくい部分もあるが、物理学からこの分野へのアプローチを考えるには、参考文献も多数あり、手頃な一冊である。(2002年 7 月 8 日原稿受付)
永平幸雄、川合葉子編著
近代日本と物理実験機器; 京都大学所蔵 明治・大正期物理実験機器
京都大学学術出版会、京都市、2001, xviii+350 p., 28.5×21.5 cm., 本体12,000円
植 松 英 穂〈日大理工〉
本書を手にとって最初に強く感じることは、カラー写真の写実的な美しさである。この写実的とは、19世紀の終わりから20世紀にかけて製作された実験機器がどのような素材から作られているか、写真でおおよその見当をつけることができるという意味である。写真に惹かれて頁をめくっていくと、一つ一つの実験装置に詳しい歴史的解説が付けられ、読み物としても手応えがある。おそらく経費の関係であると思われるが、すべての実験機器の写真がカラーではない点が少々悔やまれる。これまで本書のような実験機器を取り扱った科学史書は、海外ではいくつか出版されていたが、日本においては絶無であった。実験機器についての科学史書については、その解説はもちろん重要であるが、「百聞は一見に如かず」と言われているように写真も重要な要素である。これまでの海外の同様な出版物のカラー写真は本書のような美しいものではなかった。このことからも筆者たちの実験機器に対するこだわりが十分に伝わってくる。本書を読み進めて分かったことは、写真はプロのカメラマンによる作品であった。本書の最後に補論として、撮影についてのカメラマンの苦労話が載っている。カメラマンの作品としての考えと筆者たちの歴史的な物理実験機器としての考えの違いが分かって大変興味深い。本書に載っている実験機器は京都大学に所蔵されている旧第三高等学校で購入されたものである。現在、これらは京都大学総合博物館にすべて保管されている。その博物館のホームページでは、本書に収録してあるすべての実験機器をカラーの画像で見ることができる。しかし、それらは写実的な美しさといえるものではなく、解説もごくごく簡単なものになっていて、本書には遠く及ばない。本書の内容は三つの章に分かれていて、「第1章日本の近代化と物理実験機器」、「第2章第三高等学校における物理学教育・研究の歴史と実験機器コレクション」、そして「第3章第三高等学校由来の物理実験機器」となっている。最初の二つの章は物理教育と実験機器に関する通史で、第3章の実験機器についての当時の状況を知るうえで欠かせないものとなっている。歴史のある高校などでも古い物理実験機器あるいは実験機器の一部が残っていることがあり、本書によってそれらの実験機器がどのようなものであるか同定することが可能となろう。近代日本が作られていく途上で、どのような物理実験が教育現場で行われてきたのか知ることができる貴重な書物である。日本における最初の試みで、これだけ写真にこだわり、そして内容的にも完成度の高い科学史書が作られてしまうと、この先これを超えるものが作れないのではないかと心配してしまうほどである。(2002年 7 月 2 日原稿受付)
外村 彰
量子力学への招待
岩波書店,東京,2001, vi+92 p., 19.5×13.5 cm(岩波講座 物理の世界 量子力学1)
西 尾 成 子 〈日大理工〉
いうまでもなく、著者の外村氏は、電子顕微鏡の開発とアハラノフ-ボーム(AB)効果の検証という偉業をなしとげられたことで、世界的に知られている。量子力学の真髄に迫るこれらの業績を、ご本人が初学者にわかるように語れば、それだけでユニークな量子力学入門書ができあがるだろう。
予想にたがわず、本書は、電子の波動性の検証から始まって、クライマックスのAB効果の検証実験、磁束量子の観測で終わる。電子線バイプリズムを使ったいわゆる二重スリット実験で得られた電子線干渉図から始まって、磁束量子の対消滅を示す写真で終わる。途中に波動力学の歴史を扱った章も設けられている。
残念なのは、本書が“これまでの講座のイメージを一新した軽快でソフトな講座”全85冊の中の1冊だということ。多くの図を含めて100ページ足らずの薄い本の中で、それだけの内容を、初学者にわかるように書くのは、著者自身もいわれるように、不可能に近い。
実際、高校物理を学んだ程度の読者なら、ほとんどが消化不良を起こすのではなかろうか。たとえば、高校ではベクトル解析はもちろん物理で微積分は使われないから、大事なベクトルポテンシャルに関連した記述はわかりにくいのではないか。また、超伝導についての説明ももっとほしい。折角の磁束量子の干渉顕微鏡写真やローレンツ顕微鏡写真も、それらがどれだけ驚嘆すべき成果なのかわかってもらえないかもしれない。
もちろん、こうした消化不良は、他方で、物理をもっと勉強しようという意欲を読者に引き起こす効果ももたらしうる。とりわけ特別にすすんで物理を勉強してきた高校生や大学生にとっては、本書はきわめて刺激的である。なにしろゲージ理論からナノテクまで関係してくるのだから。
波動力学史を扱った章ばかりでなく、全体として歴史的な話題が多く取り上げられているのも本書の特徴といえよう。それは、著者の歴史心の表れでもあろうが、それによって読者の興味を少しでもそそりたいという著者のおもいの表れでもある。デビッソン、G. P.トムソン、菊池正士といった先人たちの電子線回折実験についてのエピソードには、とくに熱がこめられる。
歴史的事実が、いわゆる後知恵によって歪曲されて伝えられることは、よくあることだし、ある程度はさけられないことでもある。物理の教科書でもそのような神話がよく語られる。いちいち目くじらを立てるのはどうかと思ったが、本書も例外ではない。たとえば、有名なロイヤル・インスティテューション金曜講演でケルビン卿があげた二つの雲の一つが黒体輻射であった(p. 33)とか、マクスウェル理論がすぐには受け入れられなかったのは一つには、彼が電磁波の媒体として“得体の知れないエーテル”が存在すると言ったことによる(p. 65)、とか書かれているが、どちらも誤りであることがわかっている。
量子力学をつくってきた理論家や実験家たちの “苦闘や興奮、 情熱や執念”、に感動し、“同じ道をすすんでみたいと思う若者が出てくることを”、著者とともに心から期待したい。その際、歴史の事実をできるだけ正しく書くことは、より教育的であり、より強い感動を読者に与えるものだと思っている。(2002年 5月8日原稿受付)三田一郎
CP非保存と時間反転; 失われた反世界
岩波書店,東京,2001, viii+90 p., 19×13 cm,本体1,300円(岩波講座 物理の世界 素粒子と時空2)
宇 野 彰 二 〈KEK素核研〉
CP保存とは、素粒子の世界である現象を考えたとき、それに荷電変換(C)とパリティ変換(P)を行った現象はまったく同じように起こること、または、物質と反物質で物理現象はまったく同じであることを意味している。長い間、CPは保存していると考えられていたが、1964年に中性K中間子でわずかながらCPが保存していないことが驚きをもって発見された。本書の主題であるCP非保存は、素粒子の世界を理解する上で非常に興味深い現象であると同時に、宇宙創生を考えるとわれわれの存在自体を問う問題でもある。このことが、「失われた反世界」という副題と関係していて本書の最初に説明されている。また、昨年夏に日本と米国で加速器を使った2つの大きな実験において、中性K中間子以外で初めてCP非保存がB中間子系で発見されたので時機を得た話題でもある。前半部分で、反粒子や対称性そして最初のCP非保存の発見等が身近な例を取り上げながらわかりやすく説明されている。本書は他の素粒子の一般書と違って、主題に合うように対称性に重点をおいて書かれているので新鮮味がある。後半部分は、著者たちが大きなCP非保存を予言したB中間子系の話で、著者が直接体験した色々なエピソードを交えながら書かれているので大変おもしろく読むことができる。CP非保存を説明する基本理論を考案したのは、小林誠教授・益川敏英教授の2人である。このように、素粒子の世界で日本人が基本理論の構築、別の系での予言、実験による検証とすべてに深く関与した例はなく、そういう意味でもぜひ多くの人に読んでもらいたい本である。 (2002年3月20日原稿受付)
J. Mehra
The Golden Age of Theoretical Physics, Vols. 1 and 2
World Scientific, Singapore, New Jersey, London, Hong Kong, 2002, xix+637 p., vi+771p.
岡 田 知 二 〈白岡高校〉
"- a self-made man and independent thinker - would all of a sudden appear like a comet on the horizon of physics in 1905 and brighten the world with three gifts:" これはMehraがある人物を記したもので、3つの贈り物を挙げなくてもEinsteinのことだとすぐにわかる。Mehraの表現はどこを読んでも、この文章に通じるものがある。平易であり、イメージしやすい表現を使う点である。また、豊富な資料が使われていても読みやすいものとなっている。本書の各章をなす37編の論文、エッセイは世界各地の大学での講演を基にしたもので、MehraによるとH. Rechenbergと共著のThe Historical Development of Quantum Mechanicsは本書の改訂、拡大版であるという。この書は昨年その終巻の第6巻が出版され(その書評は、本学会誌2002年57巻 3 号掲載)、現在の量子理論の歴史研究ではその内容とともに(原論文等の)一次資料の情報を豊富に提供する重要なものである。しかし、専門家以外の人にとっては大部なものといえる。それに対して、本書は通史の要素より、特定の発見、研究を1つのテーマとして掘り下げているので歴史に興味をもつ一般の人にも読みやすい。また、業績は有名でもあまり知られてはいない人物の活躍を知る喜びも随所にある。
第1章はMehra自身が発見した若き(15, 6歳)Einstein の最初の科学的小論「磁場におけるエーテルの状態の研究について」である。Albert Einsteinを愛し励ました、母方の伯父に送られた、この小論(原文とMehraの英訳)も読め、興味をひく。相対論の起源を論じる章(第7, 8章)もあるが、全体としてはPlanckに始まる量子論(第2, 3章)、Bohr、Sommerfeldらによる前期量子論の展開(第10, 11, 13章)、 Heisenberg, Dirac, Schrodingerによる量子力学の創始(第19から23章)そして場の量子論、素粒子論の発展(第27そして29から33章)へと20世紀に発達した量子理論の歴史(1900から1940年頃まで)を中心に、現代物理学における重要な発見を1章ごとにたどる内容に編集されている。各章が独立した論文であるために、内容的に重なる部分も多々ある。他方、それが復習のような役割を果たし、各章をつなぐので、煩わしさを感じることはない。
全体を読み通して、量子力学の発見、発展により明らかとなる概念、法則の多くは既に前期量子論の研究の中で生まれていることがよくわかる。改めて前期量子論(ここでは1913年のBohrの3部作以降だけでなく、その前からの発展も含める)の存在を考えさせるものとなった。例えば、零点エネルギー、スペクトルの微細構造、排他原理そしてスピンを論じた各章などが挙げられる。物理学を自然の論理とだけ考えるなら、前期量子論は不要な存在(過去の遺物)と片づけられてしまう。しかし、本書では量子力学へ移行する際の、前期量子論による探求の活動が詳しく述べられ、その重要さがわかる。Planckは古典物理学という確固たる大建造物を捨てることへの疑念をもち、1911年に振動子がエネルギーを吸収する際は連続的で、放出する際は不連続であるという ‘第2量子仮説’ を出す。これは古典論への後退ともとれるが、一方で、新しい非古典的概念である零点エネルギーを導入することになる。その後、その存在を確かめる多くの試みがなされる。例えば、水素分子の比熱の研究は有名だが、Sternによる単原子気体の化学定数の研究はそうでもない。実験ではMullikenの帯スペクトルの同位体効果などが挙げられる。零点エネルギーは量子力学によりその位置づけが明らかになるが、Schwingerが亡くなるまで興味をもっていたCasimir効果など基底状態を持たない系の零点エネルギー効果も紹介されている。Mehraは量子力学誕生後の展開を含めた上で、零点エネルギーを基底状態のエネルギーとみなすのではなく、むしろそれまでに研究された効果を包含する指導概念、あるいは発見論的な考察であるという。前期量子論には、量子数の大きい極限での古典論との一致を指針にした対応原理という指導原理もあったが、前期量子論自体の歴史的役割はMehraが零点エネルギーについて述べたことと基本的には同じである。前期量子論は過去の遺物ではなく、現代物理学を深く理解する上で必要な存在であると思える。
Bohr理論の確証として有名なFranck と Gustav Hertz (Heinrich Hertz の甥)の共同実験は1911年に始まる。現在、学生実験でもよく行われるが、実験に対するFranckとHertzの解釈についてはあまり知られてはいない。彼らは1908 9年のStarkの解釈(線スペクトルが原子・分子のイオン化の過程に結びついて起こされ、スペクトルの振動数νは次式hν=Vを通してイオン化エネルギーVと関係するという考え)を信じ、測定結果の4.9 Vの電位差が水銀原子のイオン化を導くものと考えた。彼らがBohr理論の確証としてその研究を発表したのは1919年になってからだった。その実験の意義は大きく、1925年には彼らにノーベル賞が授与された。
20世紀はまさに理論物理学の黄金時代だったが、物理学者の国際交流も時代を築く要因だった。1911年に始まるSolvay会議は有名だが、後にBohr祭と呼ばれるゲッチンゲンでのBohrの連続講演もHeisenberg、Pauliらに大きな刺激を与えた。この講演がFermatの最終定理の証明者に贈られるWolfskehl賞(1997年Andrew Wiles受賞)のWolfskehl基金を主収入にして行われたものであり、量子論もその恩恵を受けていたというのも興味をひく。
最後に、量子力学や現代物理学の講義を受け持つ先生方が座右に置き、利用できる物理学史書として推薦する。 (2002年5月15日原稿受付)ページの頭に戻る
Physics in Perspective
Birkhauser, Basel, 1999刊、季刊、各冊平均130 p., 24 cm×16.5 cm, 年間sFr. 268(機関)、sFr. 98(個人)
小 林 澈 郎 〈福井工大工〉
広範囲の読者層を対象にその物理リテラシーを深め、歴史、哲学、人物等を通して物理学の深さとその文化的意義を伝え、物理学者と他分野の人たちとの間の深淵に橋を架けたい、と願って標記雑誌が誕生して4年目になる。寡聞にして私は物理学史や科学基礎論の専門家の批評を知らないが、あるいはプロの目からは問題にならないのかもしれない。歴史にも哲学にも暗い私はlaymanに向けた本誌の平均的読者であろうが、毎号非常に楽しんで多くを学んでいるのでご紹介したくなった次第である。
Editor-in-ChiefはJohn S. Rigden (AIP)とR. H. Stuewen (BNL)で、Editorial Boardには欧米から29人が名前を列ねる。私の知るのはD. C. Cassidy, Jamer T. Cushing, A. P. French, James Gleick, H. Kragh, N. Mermin, M. Riordan, M. L. Perlぐらいであるが、これから察して適材適所の人選に違いない。誌面構成は大別すると2頁のEditorialに続いて(1)現代まで含む歴史的な理論、実験あるいは人物に関する哲学的ないしは思想史的視点からの論考 (2)物理学と社会の関わり (3)人物評伝(対談等も含む) (4)書評。毎号ではないが(5) Physical Tourist, (6)時たまの故人回想という風である。一篇が長くても30頁程度なので読みやすい。すべて読んだわけではないが、私の印象に残ったものをいくつかご紹介しよう。
まず(1)から。最近号のR. Jackiw and A. Shimony: The Depth and Breadth of John Bell's Physics, 4 (02) 78-116. 苦労して加速器物理学者となりラザフォードラボからCERNに移って暫くして素粒子論でPh.D.を取ったBellは、たちまちCERN理論部にこの人ありという存在となる。Jackiwと名を分かつ異常性の発見は周知である。傍らBellはホビーと称して若い時から量子力学の基礎を考え続けていた。これが有名なBellの不等式に結実する。この分野の専門家Shimonyの20頁を超すFoundation of Quantum Mechanicsの部分は深く密度の濃い議論が展開されている。Jackiwによる素粒子論の業績もよく書かれている。
K. W. Staley: Last Origins of the Third Generation of Quarks: Theory, Philosophy, and Experiment 3 (01) 210-229. 小林-益川理論の歴史的背景に踏み込んで、個々の事実を正当に評価し、詳細に論じた仕事が外国人によりなされたのに驚きかつ喜んだ。ハドロンの坂田模型から牧-中川-坂田のニュートリノ混合に至る「坂田スクール」を貫く方法論的視点をよく理解して書いている。小林-益川理論を学生に講義する時、こうした一面に触れて学生が日本の仕事への理解を深める契機としたらどうか。
次に(2)からはM. Riordan: The Demise of the SSC 2 (00) 411-425. 1993年のSSC建造中止の報は今に記憶に新しいところである。National flagか、いや、国際協力だと侃侃諤諤する間に建設は始まり、予算は当初の4, 5倍に脹れる。研究者コミュニティ、国際協力態勢、連邦政府、議会等との間に生じた問題を具体的に分析して中止に至った経緯を論ずる。高エネルギー物理学に携わる者の一読に値する論考。
(3)と(2)に関わるM. J. Nye: A Physicist in the Corridors of Power 1 (99) 136-156は原爆反対を貫いたP. M. S. Blackettを描いて重い。しかし(3)のJ. Goodstein: A Convensation with Hans Bethe(対談)1 (98) 253-281弟子が回想するM. Goldberger: Enrico Fermi (1901-1954)-The Complete Physicist 1 (98) 328-336は楽しい読物である。(5)はゲッティンゲン、ウィーン、コペンハーゲン等を史家が案内するという形で昔の建物や博物館を訪ねて縁の物理学者の人と業績を論ずる。読者それぞれに曽遊の地を誌上で物理学史から楽しむのも一興であろう。会誌編集委員長が会誌3月号で、若い諸君の社会への関心の薄さを嘆いておられたが、こんな雑誌を手にとってみるのも少し視野を広げる薬にはなるだろう。(1)に属するオーソドックスな歴史や哲学的内容のものは、限られた紙幅では要約も難しく割愛せざるを得なかった。(2002年 3 月29日原稿受付)望月優子、谷畑勇夫、矢野安重監修
ビデオ 元素誕生の謎にせまる
企画:理化学研究所; 制作:(株)イメージサイエンス; カラー34分; 増補版(解説冊子付)・英語版 各2,600円(予定、税・送料別。但し教育目的に使用される場合については無料頒布あり)
滝 川 昇 〈東北大理〉
今日、宇宙の年齢は約150億年と推定されている。それと同程度あるいはそれより長い寿命の原子核を安定核と呼ぶことにすると、安定な原子核は約300種存在する。そのうち256種は、無限に長い寿命をもつ。
[短評]
それらの原子核は、縦軸に陽子数、横軸に中性子数をとったいわゆる核図表(セグレ チャートとも呼ばれる)の上に並べると、陽子の数と中性子の数が等しい対角線の近傍に位置する。それは、陽子と中性子の間に働く核力の方が陽子間あるいは中性子間に働く核力に比べ引力が強いこと、および、核子の間に働くパウリの排他原理のためである。重い安定核では、陽子間のクーロン斥力のため、中性子数が陽子数の約1.6倍になる。
一方、太陽系に存在する原子核の量は、陽子が圧倒的に多い。次に多いのは 4Heである。大まかに言えば、質量数が大きくなるにつれて存在量が急激に減少するが、陽子や中性子の数が魔法の数2, 8, 20, 28, 50, 82, 126に等しい原子核は、周りの原子核に比べ存在量が多い。
それらの元素は、いつ、どこで、どのようにして作られたのだろうか。 現在広く受け入れられているビッグバン宇宙論によれば、質量数7までの軽い原子核は、ビッグバン後の3分から15分くらいの間に作られたと考えられている(初期宇宙元素合成(primordial nucleosynthesis))。
質量数が8より大きな原子核は星の中で作られる(stellar nucleosynthesis)。その過程で鍵を握るのは、核子当たりの束縛エネルギー(正確には核子当たりの質量)が、軽い核の領域で、質量数とともに増大し、鉄の辺りで最大値をとるということである。そのため、鉄に至る軽い原子核は、様々な質量の星の中で、核融合反応によって次々と作られていく。
では、鉄より原子番号の大きな原子核は、どのようにして作られたのであろうか。ビデオの言葉を一部引用させてもらうと、「生命の誕生と存続に必要な銅や亜鉛は鉄より先にある。人類の生活に大きな役割を果たしている銀はさらに先にある。そして、金やウランは遥か先である」。
元素誕生の謎を解くためには、安定な原子核の構造や反応のみならず、安定線から離れた原子核の構造や反応の知識が必要である。過去十数年来飛躍的に発展しつつある二次ビームの核物理(不安定核の核物理)は、元素誕生の疑問に答える多くの新しい知見を提供しつつある。不安定な原子核を含めると理論的に存在が予測されている原子核は約7,000種あり、そのうち約3,000種は、実験的にもその存在が既に確認されている。不安定な原子核は、核図表の上で安定核の周りに分布する。
本ビデオは、二次ビームの核物理で世界をリードしている理化学研究所の研究者らが、核物理学および宇宙物理学における最新の研究成果を取り入れて、元素の誕生と進化の謎解きの到達点を編纂したものである。コンピューターグラフィックスを活用し、美しい画像によって、核宇宙物理学(Nuclear Astrophysics)と呼ばれる研究分野の基礎的な事柄から研究の最前線までを印象深く伝えている。特に、ハイゼンベルクの谷(束縛エネルギー、正確には1核子当たりの質量、を考慮して原子核を配置した図における谷間)に沿った、軽い元素から重い元素に至る元素合成の立体的な旅の出来映えは圧巻である。
ビデオは、核物理学や物理の専門家のみでなく、院生や学生、さらには、高校生にも十分楽しめる。元素生成に関する研究の現状を学んだり、大学や高等学校での教材として使うなど、様々な形で活用されることを是非勧めたいビデオである。
今回改訂された増補版では、ビッグバンの後宇宙が膨張とともに冷却し、一万分の1秒くらい経ったときに、クォークから核子が作られていく様子や、重い星の中で進行するCNOサイクルと呼ばれる核反応サイクルの映像が加えられ、また、鉄からビスマス(Bi)に至る元素生成の主要な過程の一つであるゆっくりした中性子捕獲反応(s-process)およびその中性子源としての赤色巨星の記述が詳しくなった。さらに、ウランなどBiを超える重元素を生成する有力な候補と考えられている超新星爆発についての詳しい説明が加えられ、また超新星爆発の数値シミュレーションが新しい映像におきかえられた。
増補版に添付された解説書には、ビデオに現れる代表的な図が掲載され、入門書としても教育的資料としても読みやすく書かれている。内容に少し触れてみよう。まず最初に現れる生命との関連を取り入れた元素の周期律表は極めて新鮮である。ビデオの中でも語られる元素の誕生と生命との関連で活用すると面白い。解説書執筆者の言葉を借りれば、「地球に生命が誕生したのは、非常に幸運な偶然の重ね合わせだったのだと実感した」。ビデオを鑑賞される方々が、元素誕生のドラマを楽しむと同時に、同じような実感をもたれることを期待したい。この周期律表は、また、高等学校などの教材としても是非役立てたい資料である。解説書の最終節「我々が存在する偶然の幸運」も印象的だ。拙文で改めて紹介するより、解説書の項目を原文のまま転載するのが賢明であろう。曰く:「もしも太陽がCNOサイクルによってエネルギーを放出していたら人類は存在しただろうか、原子と原子核の魔法数が一致していない幸運、原子核を形づくる核力の微妙なさじかげん、もしもrプロセスでウランが生成されなかったら?、星の内部で炭素12が合成された幸運、そして行き着く先は」。ビデオはこれらの事柄を見事に紹介している。
解説書の最後の文を借りて、この紹介文を締めくくるとしよう。「21世紀初頭の今日、天文観測、原子核実験、理論の進歩によって、元素の起源を探る研究は最もエキサイティングな時期に差しかかっているといえよう。」
最後に、本ビデオは、第42回科学技術映画祭(2001年)において文部科学大臣賞に輝いたこと、第39回日本産業映画ビデオコンクール(2001年)においてビデオ賞(学術研究部門)を受賞したこと、既に英語版が完成し、ドイツ語にも翻訳される予定があることを付け加えたい。英語版のタイトルは、“Element Genesis-Solving the Mystery"で、監修にオハイオ州立大学のボイド(R. Boyd)教授が加わった。
増補版および英語版は、高校・大学の授業などの教育目的に使用される場合に限り、理化学研究所より無料で頒布を受けられる。この教育目的のための無料頒布を希望する場合には、氏名、勤務先の住所、電話・ファクス番号、Eメールアドレス、使用目的(具体的に)、日本語版希望か英語版希望かの区別を明記の上、理化学研究所 広報室 元素ビデオ担当まで、Eメールかファクスにて申し込む(Eメールアドレス:koho@riken.go.jp、FAX番号:048-462-4715、問合せ先電話番号:048-467-9272)。また教育目的以外での使用や、個人的に購入を希望する場合は、イメージサイエンス社ホームページhttp://www.image-science.co.jp/element/を通して購入できる(問合せ先電話番号:03-3404-7817)。(2002年 4 月30日原稿受付)
M. ジョルジュ著、盛田常夫編訳
異星人伝説; 20世紀を創ったハンガリー人
日本評論社、東京、2001, xviii+320 p., 21.5×15 cm, 本体2,900円
植 松 英 穂 〈日大理工〉
最初の原爆製造計画であるマンハッタン計画においては、シラードをはじめとする何人かのハンガリー人たちが関与していた。日本では知られていないが、欧米では彼らは異星人と呼ばれ、特別な目、すなわち優秀な民族であると見られているという。この異星人という伝説が生まれたのは他ならぬロスアラモスであったらしい。本書は、書名からSFのような印象を受けるかもしれないが、20世紀に綺羅星のごとく活躍した20名のハンガリー人たちの伝記である。著者のマルクスはエトヴォシュ大学名誉教授(専門は原子物理学)で、本書においてこの伝説を実証しようとした。全体は三部に分かれ、第一部では伝説のいわれを、第二部では彼らが書き残したものやマルクスによる彼らへのインタビューから引用して思想や人となりを、そして第三部では異星人を生んだ背景としてのハンガリーの教育システムを記している。その教育システムにおいては、才能発掘のためのコンテストという競争原理の重要性が主張されているところが興味深い。本書で取り上げたハンガリー人たちのほとんどが、米国などで活躍してきたことから、マルクスが「ハンガリー社会が自らの才能を正しく評価・尊敬するように成長することを願う。」と締めくくっているところに哀愁が漂っている。(2002年2月28日原稿受付)
A. Pais, M. Jacob, D. Olive著、藤井昭彦訳
反物質はいかに発見されたか?; ディラックの業績と生涯
丸善、東京、2001, 19×13 cm, xvi+126 p, 本体1,900円
仲 滋 文 〈日大理工〉
ディラックは20世紀最大の物理学者の一人であり、英国の物理学史の中では、ニュートン以来の偉大な学者と言える。しかし、1984年にディラックが没した時には、タイムズ紙が短い追悼文を報じたのみで、国はさしたる関心を抱かなかった。国がその偉大さを認め、遅ればせながらウエストミンスター寺院にディラックの顕彰碑が奉献されたのは、1995年のことである。本書には、式に先立って王立協会で行われた記念講演の中の三つの講演と、奉献式でスチーブン・ホーキングの行った一場の講演が収録されている。
[短評]
本書の各章は、それぞれの講演に対応し、その第一章は、科学史家としても知られるエイブラハム・パイスによる、「ポール・ディラック、その生涯と業績」である。理論物理学の“黄金時代”を築いた一人であり、パウリをしてアクロバティックと言わしめたディラックであるが、その全体像は以外に知られていない。パイスの講演は、ディラックの受けた物理教育、方程式の調和を意識した研究の手法、寡黙で孤高の人間性が形成された遠因、さらには物理を離れた日常のエピソードなどが、物理学を志す者の琴線に触れる語り口で、巧みに述べられている。同じ記事がパリティに分載されているが、本書の訳文は細部において手が入れられ、読みやすいものとなっている。
第二章は、CERN(ジュネーブ)のモーリス・ジェイコブによる「反物質」である。ディラックにより扉の開かれた反物質の世界の話題で、空孔理論が提案された当時の雰囲気を伝える部分もあるが、多くは高エネルギー物理学における反粒子物理を、実験家の立場から解説したものである。「素粒子の本質にかかわる最も決定的な発見(ハイゼンベルグ)」と言われる反物質を題材として、現代の高エネルギー加速器研究の目指す方向、宇宙論との関わり、さらには反陽子を用いた医療の可能性など、さまざまな話題が語られている。最後の章は、ディラックが予言したもう一つの粒子である磁気単極子について、その現代的な発展を述べたディビット・オリーブの「単極子」である。現代の素粒子理論に現れる、非可換ゲージ理論、自発的対称性の破れ、超対称性、弦理論などが、実は単極子をキーワードに深いところでつながりを持つことが語られる。専門的な内容ではあるが、話題として興味を持たれる方も多いであろう。
個人的には、本書は第一章を読みたさに買う種類の本であるが、どの章も一読の価値はあり興味深い。ただ、元々第一章に付いていた140編あまりの資料索引は、“一般書”という理由で割愛されている。パリティ掲載版の資料を見ると、もしそれが割愛されていなければ、本書の価値は一段と上がったことであろうと思われた。(2002年2月1日付原稿受付)
栗野輪美、田島紀子、田鍋和仁、乗本祐慈、福江 純
マルチメディア宇宙スペクトル博物館〈可視光編〉天空からの便り
裳華房、東京、2001, 46 p., 25.5×18 cm、本体4,500円(CD-ROM & ガイドブック)
前田京剛 〈東大総合文化〉
昨今大学に入学してくる学生たちにとって、宇宙は人気の高い分野のようで、物性物理を専門とする我々は、分野のアピールに苦労する。とくに、宇宙の分野は、ビジュアルな図や写真などを豊富に用いたプレゼンテーションが容易かつ非常に効果的で、それがまた現代の若者の心を捉えるようだ。本書はCD-ROMとそのガイドブックからなり、博物館に入館して、好きなコーナーを見るという形をとりながら、「スペクトル」とは何か、それを用いて天文学者がどんなことを解き明かしてきたかを、中学生・高校生そして、我々のように、物理を専門とするものの宇宙物理はやや遠いというものといった、あらゆる階層の人々に楽しみながら理解してもらえるよう、専門家が力を入れて作成したもので、〈X線編〉〈電波編〉につぐ3作目である。子供のころ、星の図鑑を見るのは好きだったが、「スペクトル」という言葉が出てくると、急に難しくなってしまったという記憶がある。本書では、そのような子たちのために、「身のまわりの世界」、「色相・明度・彩度」といった項目も設けて、丁寧な説明がされており、至れり尽くせりといった感じである。こんな本が昔あったらよかったのにとおもうとともに、物性物理学者も、このような努力をみならわないといけないと感じた。(2002年1月11日原稿受付)
[短評]
関 昌弘編
核融合炉工学概論; 未来エネルギーへの挑戦
日刊工業新聞社、 東京、 2001, xiv+246 p., 21.5×15 cm、 本体3,200円
門 信一郎〈東大高温プラズマセンター〉
核融合開発ほど物理学・工学両面において長期に及ぶ研究が必要とされる課題は科学史上類を見ないのではなかろうか。 国際熱核融合実験炉ITER誘致の是非に関する論議が高まってきた今日、 50年近くに及ぶ核融合炉開発研究の現状、 到達点、 課題が総説されている 「核融合炉最前線」 ともいうべき本書が出版されたことは特筆すべきであろう。 初めの約1/4を占める第1部は核融合の原理と実現までの具体的なシナリオの解説であり、 続く第2部は超伝導コイル、 真空容器、 加熱及び電流駆動装置、 計測制御、 ブランケット、 プラズマ対向機器、 燃料循環、 遠隔保守、 安全技術の各論である。 これらは原子力研究所に属する各分野の研究者によって、 専門的でありながら理工学系の学部学生にも理解できる程度に丁寧に記述されている。 核融合炉工学の初学者対象には講議・ゼミの教科書・参考書として適当であろう。 加えて、 評者を含め炉工学を専門とはしていないプラズマ研究者及び核融合研究の黎明期を“体験できなかった”若手研究者には核融合開発の全体像を把握するために、 ITER問題を工学的側面から考えてみたいと思われる方々には“叩き台”として一読を勧められる良書である。 強いて言えば、 物理学を専攻とする読者という観点から見て、 プラズマ閉じ込めの現状と諸問題についてももう少し紙面が割いてあれば炉工学にとどまらず核融合開発、 ITER計画をより総合的に理解できるのでは、 という印象を持った。(2002年1月16日原稿受付)
阿部龍蔵
物理を楽しもう
岩波書店、 東京、 XII+228 p., 19×13 cm, 本体2,500円
西 條 敏 美〈徳島中央高〉
「岩波基礎物理学シリーズ」 には、 本来の物理の話の他に、 肩の凝らない閑話休題的な読みのもとして、 coffee breakという欄が設けられている。 この欄は本文よりもはるかに面白い読み物になっているので、 「本文とcoffee breakの役割を逆転させれば、 物理を楽しみながら学べるのではないかという発想が本書執筆の出発点」 になったという。 その発想で書かれた本書は成功していると思う。
力学から原子物理へと数学的展開を主体とした体系的物理の本も、 これから物理を専門にしようとする一部の学生にとっては必要であろうし、 ごく一部の人にはこれも楽しむ物理となり得るかもしれない。 しかし、 多くの一般市民を物理から遠ざけてしまった大きな要因は、 数学的展開を重視した旧態依然とした物理教育が高校や大学で行われ、 物理の本といえば、 教科書も含めてそのような本が多かったことにあると思われる。
誰にとっても親しみやすく楽しむ物理にするためには、 少なくとも3つの視点が大切であろう。 第1は、 数学的展開を重視するのではなく、 題材として身近な物理的事物や現象を取り上げること、 そしてそれらがふつうの良識でどれだけ説明し得るかを記述するこ とである。 第2には、 物理の概念や法則などを取り上げる場合でも、 その成り立ちについて十分に説明すること、 第3には、 科学者の知的営みについても記述し、 物理が日常生活にどのように役立っているかということも記述することである。
本書は、 このうちの第1の視点で構成されている。 章立てを見るとそのことがよくわかる。
1. 乗り物のおもちゃ 2. リハビリの一工夫 3. ジャンプの力学 4. 弓の名手たち 5. けん玉入門 6. 0℃ 以下を実現する 7. トランプと麻雀 8. 静電気との出会い 9. 電池と電流 10. 磁石の超能力 11. 家庭の電気 12. 2本の鉛筆
第2の視点についても、 著者自身が現れてそのことに言及している箇所もある。 著者はいう。 「物理そのものを学ぶ他に物理に関する歴史を知ることは、 物理を楽しむ1つの方法だと考えられます。 特に熱学の場合その歴史には紆余曲折がありましたので、 科学史の勉強は有益と思われます。」
わかりやすい文体で書かれ、 どの章からでも自然に入っていけた。 第1章から読んでいかないと後が理解できないような構成では、 広く一般市民が楽しむ物理にはならない。 (2002年1月8日原稿受付)D. M. Cannell
George Green, Mathematician & Physicist, 1793 1841, The Background to His Life and Work, 2nd Ed.
Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), Philadelphia, 2001, xxxiv+316 p., 22×14 cm, $55~70
河 合 潤〈京大院工〉
Green関数を道具として使っている周りの何人かに聞いたところ、 Greenがどういう人かよく知っている人も勿論いたが、 全く知ないという人の方が多かった。 本書は英国の仏語教師の著作で、 1993年の初版を大幅に増補したものである (本文180ページ、 付録120ページ)。 1993年にGreen生誕200年祭が行われたが、 第2版にはこのときのJ. SchwingerやF. Dysonの講演も収録されている。 Greenの業績は 「ポテンシャル」、 「グリーンの定理」、 「グリーン関数」 など多い。 ほとんどはノッティンガムの粉ひき屋の彼が三十代後半に出版した処女作 「エッセイ」[An Essay on the Application of Mathematical Analysis to the Theories of Electricity and Magnetism (1828)]に記述されている (京大には物理学科の図書室に1889年の複写版が1冊だけ所蔵されており貴重書として鍵つきの書棚に保管されている)。 Greenはノッティンガムのパン屋の息子で、 9歳のとき父親を手伝うために小学校をやめ、 その後自力でラプラスの「天体力学」などを仏語で読み、 上述の 「エッセイ」 を書いた。 肖像画のたぐいは残っていない。 粉ひき屋が教育も受けずどのようにして 「エッセイ」 を書くに至ったか、 残された書簡などによって明らかにしようという著者の努力にもかかわらず、 依然なぞの多い人物である。 荒れ果てて残っていたGreenの粉ひき風車が、 ノッティンガム大学のL. Challisの努力によって科学博物館となったいきさつも書かれている。 「エッセイ」 は、 Gauss, Chasles, Sturm, Thomson (Kelvin卿) によって同じ定理が再発見された後の1845年まで知られることがなかった。 21歳のThomsonは、 1845年Cambridge大学の卒業試験を終えてパリ留学に発つ直前に 「エッセイ」 を入手、 旅行中熟読し、 パリ2日目 「エッセイ」 を手にLiouville宅を訪問した。 その夜Sturmが 「エッセイ」 を見せてほしいとThomsonの宿を訪ねてきてAh voila mon affaireと大声で叫んだ、 というKelvinの手紙も収録されている。 巻末の付録には 「エッセイ」 の要約もある。 英国の大学に関する固有名詞が多く読みずらいが (Tripos, Wranglerなど)、 小さな英和辞書でも詳しい訳語が出ている。 「エッセイ」 出版後GreenはCambridge大学に入学したが1841年に病没した。 学生時代、 歴史的背景も合わせてGreen関数の講義を聞いていれば理解も早かったであろうにと、 当時の教官を恨んでいる。 大学の講義でグリーン関数を教えている方にはぜひ活用していただきたい書物である。 Greenの生涯についてはS. Doniach and E. H. Sondheimer, “Green's Functions for Solid State Physicists", Imperial College Press (1998)やS. P. Timoshenko, “History of Strength of Materials", Dover (1983)などにもごく短く紹介されている。 本書を読む時間のない方はこれらの本を参考にされるのもよいであろう。 (2001年10月19日原稿受付)
J. Mehra and H. Rechenberg
The Historical Development of Quantum Mechanics, Vol. 6; The Completion of Quantum Mechanics 1926-1941
Springer-Verlag, New York, Part 1: 2000 and Part 2: 2001, xxxvi+1,612 p.
後 藤 邦 夫
このシリーズの第1巻が出たのは1982年である。 20年を経て完結編が出版された。 第1巻の冒頭には著者のひとりMehraによる約40ページの序文がある。 そこには1952年にPauliとHeisenbergに鼓舞されて研究が始まり、 1970年にMehraとRechenbergがテキサス大学オースティン校に滞在中にHeisenberg の勧めでこの大著の執筆が開始されるに至った経過が、 全巻の構想とともに記されている。 本書では、 刊行された論文だけではなく、 各地のアーカイブ、 特にThomas Kuhn の主導下で進められたSources for History of Quantum Physicsの成果が資料として用いられた上に、 著者らによる大量のヒヤリングの結果が利用されている。 それにはPauli とHeisenbergのバックアップが極めて有効だったに違いない。 結果として、 いくつかのテーマに関して類書を抜く詳細な記述が可能となった反面、 その記述自体がコペンハーゲン学派中心の 「正史」 の性格を持つに至った。 この第6巻は量子力学の完成後の歴史であるから特にその傾向が強い。さらに、哲学的テーマも社会的テーマも最小限に抑えられ、 長期の歴史的視点も充分ではない。 本書の評価が大きく分かれる所以である。
第1部は1926年から1932年までを扱い、 第1章で確率解釈と変換理論の成立、 第2章で不確定性原理、 相補性、 Dirac電子論と場の量子論の成立を扱う。 第3章は経験的基礎と数学的基礎と題され、 前半は主として観測論を含むvon Neumannの仕事と群論の話、 後半は物性論から原子核におよぶ具体的テーマである。 特に第2章のコペンハーゲン解釈の成立に至る記述が面白い。 マトリクス力学を出した直後のHeisenbergにEinsteinが仕掛ける哲学的論争から、 Bohrが最初にComplemetarityを系統的に論じたComo Lectureまで、 Schroedinger, Pauli, Diracを交えた対話、 論争を通して当事者たちの思考の経過がトレースできる。
第2部は、 第4章 「量子力学の概念的完成と拡大」 から始まる。 その前半は不確定性原理に触発された因果性論争とBohrの相補性、 ERPパラドクス、 Schroedinger Cat等に関わる論争にあてられる。 章の後半は素粒子、 原子核、 宇宙線、 固体物性、 極低温、 超高温などへの量子力学と場の量子論の適用の歴史である。 ここで、 不確定性と相補性をめぐる多くの哲学的議論が登場するはずであるが、 Moritz Schlick とHeisenbergの対話だけが取り上げられている。 相補性に関するBohrの初期の記述のあいまいさに対してはSchlickと同じウイーン学派のNeurathが厳しく批判しBohrも積極的に対話に応じた。 そして、 彼は1936年のコペンハーゲンでの 「精密科学と認識論」 の国際会議に出席し講演するのである。 (この会議の話題も相補性、 ERPパラドクス、 von Neumannの観測理論などであった。) 本書にこれらの記述が欠落しているのは哲学関係の雑誌 (たとえばErkenntnis) やアーカイブが著者らの視野の外にあったからであろう。 一般に量子力学に関する物理学者の哲学的発言は多く、 本書にもかなり記載されている。 しかし彼らと哲学のプロとの対話をもより多く記録すべきであったと思う。
第2部の後半の約200ページはエピローグとして1942年から1999年までの主な話題が整理されている。 その過半は、 S行列、 QEDとくりこみ理論、 標準理論の成立史が占めている。 ただ、 これらのテーマに関する既刊の歴史書は多く、 それらと比べると相当に簡略化されている。 最後の100ページで 「実験室と宇宙における量子効果」 と 「量子力学解釈の新局面」 が扱われる。 可能なかぎり多くの話題を入れようと努力した点は評価できるが、 いかにも紙数不足である。 Aspectの実験や多世界解釈、 disentangled statesに言及しており、 AB効果が紹介されながらTonomuraの実験は出てこない。 確率過程量子化、 位相の量子論、 量子カオスなどの記述もない。 その意味では現代につながる部分は満足すべきものではない。 末尾の量子論研究者の4世代に関する短い文章は 「Heisenberg, Pauli, Dirac, そしてYukawaがくりこみをついに受容しなかった」 という指摘などを含み、 それなりに面白い。
本書はこの種の歴史書としては読みやすいほうである。 そして、 一見奇妙に見えるコペンハーゲンの正統派の立場を理解する上で、 未整理な観がある第2部よりも第1部が有益であろう。 日本人の寄与についての記述は必ずしも十分ではない。 「日本における量子力学の発展史」 が必要かもしれない。 ただ、 かつてPauliが本書の著者Mehraに言ったとおり、 「量子力学の歴史を学ぶには量子力学と場の量子論に精通する必要がある。」 それに、 日本の研究者が著者たちのようなパワーを多年にわたって持続することができるであろうか。 また、 長期にわたって彼らを支えたような仕組みが我が国に存在するであろうか。 (2001年10月31日原稿受付)江 沢 洋
理科が危ない - 明日のために -
理科を歩む - 歴史を学ぶ -新曜社、 東京、 2001, 206 p., 19×13 cm, 本体1,800円
新曜社、 東京、 2001, 206 p., 19×13 cm, 本体1,800円
並 木 雅 俊 〈高千穂大〉
この2冊の本は、大学人の職種とされる教育と研究に関する物理屋のためのエッセイ集である。『危ない』には教育に関する22篇が、『歩む』には物理の理解の奥行きに関わる21篇が所収されている。 計3篇ほどの書き下ろしはあるが、 ほとんどは過去10年間に書き溜めたエッセイの再録である。このためしばしば同じ話がでてくるが、読んでいてそう気にはならなかった。何故だろう。著者の人生観がここに記されているからだろうか。読後、これら2冊は本で育った碩学である著者の半生記なのだろう。そう感じた。
『危ない』 を読みながら、「賑わう部屋からは外はよく見えない。少し部屋を暗くして静寂にすれば外がよく見える」という佐藤文隆さんの言を思い出した。明日を見るには、問題を抱えた現在からの方がいい。著者のねらいもこんなところにあるのだろう。 このため、書名から連想される思い込みや感情をぶつけた本ではない。 まるでファインマン本を読んでいるかのような、爽やかささえ感じた。
著者は、巷に流布する教育論を視野狭窄であるという。学校を出てから一度も使わない2次方程式、それに漢字の書順など教えなくてもよい、といった論者に与みしない。 世俗の尺度・価値を学校という小世界に持ち込んではいないか、過去の失敗に学ぶといった歴史の視点が欠落してはいないか、と判定条件を提示する。 それに「勉強することは教わることだ。近年の大学生が、そう思い込んでいる」 という。その通りだと思う。 学校を取り巻く環境がそうなのだから。テニスを始めようとするとまずはテニス教室、 英語を話したいので英会話学校へ…。どうも誰かに教わらなくては、何事もできるようにはならないと思い込んでいる。こんな学び方が、習い性になってしまった。社会の学問温度を高くしなくてはならない。
『歩む』 は、特に若手の方々に読んでほしい本である。特に、「物理学の50年」 と「仁科芳雄の切り開いた道」は、日本の物理学の概要を知るによき道しるべとなろう。
この書は、‘わかるとは何か’から始まる。「原論文を読み、教科書を読んで論理的にわかったつもりでも、なお不安が残るというところは理科教育にも考えるべき点を示唆している」とし、 教師は「内容にリアリティの肉を盛り上がらせろ」という。論争の歴史を語ってみるのも一つの手段だと例示する。科学史を学ぶことは、「物理学の講義が論理的構成の筋を追うのに対して、その筋を、場合によってはいくつかの筋に並べて、 横から眺めて比較・論評する」ことにも効用があるという。線だけではなく、幅をもって‘わかる’のである。なるほど。
2冊を読み終えて、 江沢さんがわかった、 ような気がした。 それに執念ともいえるこだわりを知った。17年前に休刊し未だに復刊していない雑誌 『自然』 のことである。 愛読者であったために侘しさも一入なのだろう。 同感である。 そういえば、 書店の科学書の棚も小さくなった。この国の科学温度が下がっている。著者の「日本のようにユトリができて理科の授業を減らそうという段階に達した国は、アジアといわず世界にも二つとないのではないか?」 には、 評者は‘ない’と答える。この2冊で使用されている 「理科」 はすべて 「物理」と置き換えて読むとよいだろう。蛇足ですが。 (2001年9月11日原稿受付)M. フレイン著、 小田島恒志訳
コペンハーゲン
劇書房、 東京、 2001, 206 p., 19.5×13.5 cm、 本体1,905円
中 村 孔 一 〈明治大法〉
映画のアカデミー賞に対応するアメリカ演劇界の大きな賞であるトニー賞の作品賞を受賞した戯曲の翻訳。 登場人物は、 ボーアとハイゼンベルク、 それにボーア夫人のマルグレーテの3人。 謎の多い1941年秋のハイゼンベルクのボーア訪問が主題とあって、 2000年5月のブロードウエイでの幕開けは、 畑違いの物理学者や科学史家を巻き込んだ騒ぎになる。 ニューヨーク市立大では、 ベーテ、 ホイーラー、 科学史のホルトン、 キャシディらを集めて、 この戯曲の背景を議論するシンポジウムが開催される (Physics Todayの2000年5月号に関連記事が掲載されている)。
1941年9月、 ナチ・ドイツのポーランド侵攻に始まったヨーロッパの戦争は3年目に入り、 ヨーロッパの大半を支配下に治めたナチ・ドイツはその絶頂期にある。 アウシュビッツのガス室が使われ始めるのもこの9月。 そうした時期に、 ハイゼンベルクは、 ドイツ占領下にあるコペンハーゲンにボーアを訪ねる。
ヒトラーが原爆を持つことの恐怖が、 アメリカの原爆開発の出発点にあったことはよく知られている。 そして,もしドイツが原爆の開発を進めているとしたら、 ハイゼンベルクはその中心にいる一人であろうと誰もが考えていた。 事実、 ハイゼンベルクは開戦と同時に始まった陸軍兵器局の核分裂プロジェクトに動員される。
そうした状況下で、 ハイゼンベルクは何故ボーアに会いに行ったのか。 そこで二人は何を話し合ったのか。 当人や関係者たちの戦後の言明は微妙にくい違っている。
「でも、 どうして?」「どうして彼はコペンハーゲンに来たの?」というマルグレーテの科白に始まり、 この謎をめぐって戯曲は繰り広げられる。 といっても、 登場人物の三人はすでに死者であり、 その後のマンハッタン計画の成功も、 ドイツが原爆を作れなかったことも知っている。 それにもかかわらず、 「でも、 どうして」 という問いは残る。 時間を行きつ戻りつしながら、 彼らは何度も何度も 「あの時」 を再現する。 その度に、 答えは違う。何を見るかで、 見えるものは違ってくる。 いわば、 戯曲自体が量子力学的に展開していく。
芝居としての面白さは、 科学史的な興味だけにあるわけではない。 ボーアとハイゼンベルクの間の、 時には反発を含んだ 「父と息子」 的な情愛、 それにいらだつマルグレーテ。 そして、 この微妙な3体問題に、 事故で亡くしたボーアの息子の影がちらつく。
2001年11月には、 東京の新国立劇場でも上演されたので、 御覧になった方も多いかと思う。 私も楽日の舞台を観た。 初めは、 ボーアやハイゼンベルクを日本人の俳優が演ずることの違和感はあったが、 いつの間にか、 舞台の上で交わされる長科白の応酬に引き込まれていた。 やはり、 よく書けている芝居だと思った。
この本には、 50頁を超える長大な 「作者あとがき」 (net上にも公開されている) が付いているが、 この部分だけでも読む価値があるように思う。 (2001年9月28日原稿受付)
ページの頭に戻る