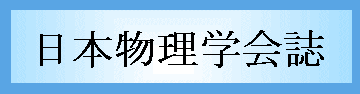
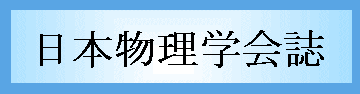
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を紹介者のご了解の上で転載しています。 ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。 また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
恒星社厚生閣,東京,2006, ix+172 p, 21×15 cm, 本体3,300円(Einstein Series Vol. 5)[学部向・一般書]
柴田晋平
宇宙の灯台; パルサー
日比野欣也 〈神奈川大工〉
パルサーは、1967年にアントニー・ヒューイッシュとジョスリン・ベル・バーネルによって発見され、この功績により、ヒューイッシュは1974年のノーベル物理学賞を受賞した。そんなこともあり、ブラックホールと同様にその名前だけは意外と多くの人が知っているようである。それでも日本語でパルサーに関してのみの書物を見かけることはないので、ある意味で快挙かもしれない。
さて、本書はそのパルサーの発見の歴史から始まり、パルサーの正体を掴むあたりを導入部としている。その後は、パルサーがパルサーたるゆえんであるパルス状の信号(放射線)の発生メカニズムに関して、順を追って分かりやすく解説されている。途中、パルサーが宇宙発電所になっているということを、ネオジム磁石を使った(一見簡単な)実験を試行錯誤しながら、解説しているところは大変興味深い。
後半はパルサー磁気圏での粒子加速の話に入っていくが、ここでもできる限り数式に頼らず、直観的なイメージでうまく解説している点は感心する。最新の観測データも取り入れながら、パルサー磁気圏の極限状態が目に浮かぶような工夫が随所になされている。これは裏返せば、パルサーに関しては分かっていることより、まだ分かってないことの方が多いことを示しているのかもしれない。著者のアイデアもたくさん紹介されているので、後は読んだ人が判断すべきであろう。個人的には、10年後20年後と本書が改訂されていくのを楽しみにしたい。
本書は一般向けに書かれており、専門家が読むには少々物足りないと感じる点があるかもしれないが、この分野の全体を眺めるには非常に良い本である。ただ、回転駆動型パルサーだけでなく、連星系パルサーやマグネターなどの話題まで網羅して欲しかった。さらに欲を言えば、文中で紹介された文献のリストや、「さらに興味がある人」のための参考文献などが文末に紹介されていると良かったと思うのだが、このシリーズの主旨とか、ページ数の制限とかで難しかったかもしれない。
いずれにせよ、パルサーという奇妙な天体にちょっとでも何か感じる人は是非読んでいただきたい。読み物としては十分に面白い。この宇宙の灯台を頼りに、より一層、宇宙に関心を持つことは間違いないだろう。
(2006年10月5日原稿受付)講談社,東京,2006, 374 p, 17.5×11 cm, 本体1,150円(ブルーバックス)[一般書]
山本明利,左巻健男
新しい高校物理の教科書
栗 田 和 好 〈立教大理〉
本書は現代人の教養としての理科の普及を目指し高校レベルで編集したシリーズ全4巻のうち物理分野を扱った1巻である。主たる読者として想定されているのは題名どおり高校生であるが文系の生徒や社会人も対象としている。
構成は不人気といわれる教育指導要領に準拠せず新課程の検定物理教科書とは一線を画している。力学、熱力学、波動、電磁気、原子・原子核、現代物理の順にストーリーを展開して原子で構成される物質観を無理なく理解できるように工夫がなされている。
内容は各節の冒頭にまず3つほどのクイズがあり、わかりやすい説明を進めていく途中で自然に問題が解き明かされていく。最初に疑問を抱かせ一気に読者を引き込む力量には特に感心させられる。最も素直な直感的説明を心がけ各節でわからせることにほぼ成功しているといえる。
ところどころにちりばめられたコラムでも興味深いエピソードや現代的な話題を提供していて効果的である。特に「式変形で導かれる複数の公式はすべて暗記せず導き出せるようにしておくこと」など教科書にはまず書かれていない心得などが随所に見られ初学者に対する著者の心遣いが感じられる。
ただ、出版社のシリーズの制約のためとは思われるが、新課程の物理教科書がほぼ全面的にカラー刷りになったのに対して本書の図がカラーでないことは残念である。巻末の参考文献のリストは発展的な勉強を志す読者によい指針を与え非常に効果的であると感じた。索引も必須である。
全般的に掲げる目標の達成に成功している本書であるが更なる改善のために以下の3つの注文をつけたい。①300ページを読破してたどりついた原子とそれ以降の記述があっけなく終わってしまう印象があるのでより詳しい記述を望む。特に最後の節で現代物理の醍醐味である「素粒子と宇宙」を扱っているが、そこに3ページしか割いていないことは非常に残念である。②物理を目指す読者にとってはやはり良質の問題をじっくり考える必要があるので問題数を絞って巻末にまとめてのせてほしい。③電車の中で読む時は各節の問いから答えまで一続きの時間が取れるとは限らず、立ったままページを戻りづらいこともあるので、答えを示すところで問いの内容を再掲してほしい。
本書はわかる楽しみを知ってもらう意味ですべての高校生に授業で使う理科の教科書に加えて読んでもらいたい一冊である。また、大学や社会で物理をわかりやすく説明しなくてはならない機会が増大している現在、本書は専門家にとっても強い味方になってくれるに違いない。また、高校までの物理の理解に不安があるという理工系大学生や好学の社会人の良き自習書としても活躍してくれるものと確信する。
(2006年8月31日原稿受付)
東京大学出版会,東京,2005, xii+195 p, 21.5×15 cm, 本体3,200円(非線形・非平衡現象の数理② 三村昌泰監修)[大学院向・学部向・一般書]
松下 貢
生物に見られるパターンとその起源
西 森 拓 〈広島大理〉
本書の目的は数理科学的手法によって生物におけるパターン形成のダイナミクスを記述することである。その最大の特徴は、完成した数理模型の提示よりも、素材(=現象)の捉え方や模型としての表現法を示し、さらに複数の模型の比較検討や失敗例などを通じて「模型作りの手ほどき」をしているところにある。生物のような複雑な対象の本質を理解するには模型を通じた現象の解釈が重要であり、実験との連携の仕方や模型の構成法そのものが問われる。本書は、模型作りの魅力を伝える新しいタイプの「ガイドブック」といえる。
具体的な内容として、第1章では、バクテリアコロニーのパターン形成を扱っている。2人の執筆者が実験と理論の両面から現象に切り込み、模型作成という切り口による共同作業の手本を示している。ここでは、バクテリアの集団の振る舞いを電析実験などと類似のものとして捉えられており生物独自の論理が前面には出てこないが、バクテリア集団の複雑な時間発展を記述するためにどのような側面に目をつけて実験や観察をするべきか、そこから数理模型にいかに持ち込むか、できあいの結果だけでなく方程式の項ひとつひとつの「こころ」まで伝えようとする気遣いが感じられる。
第2章ではチョウの羽の模様や擬態について、第3章では魚の縞模様、葉脈形成、網膜形成などを取り扱い、ともに生物表面で見られるパターン形成の過程を扱っている。これらの2つの章の基本的アイディアはチューリングの拡散不安定性にあるが、本領はむしろチューリングの恩恵にどっぷりつからないところに発揮されている。すなわち、生物独自の機構-細胞間の接着力や遺伝子の局所的発現の仕方など-についての現時点での実験的な知見を紹介し、これと数理模型がどのようにしておりあいをつけるのか慎重に議論しているところにある。生物の内部機構を無視したマクロな数理模型が現象の本質をはずしていた例も興味深い。
第4章はおもに生物内部での形態形成を論じている。ここでは、先の章よりさらに注意深く生体内部の分子反応機構を取り扱っている。とくに各細胞の相互位置決定について拡散場を利用したタンパク質の局所的発現機構やシグナル分子と受容体の相互接着機構を分子反応と関連づける形で説明がなされている。先の章同様ここでも模型作成の過程がふんだんに紹介されており、生物のミクロな機構を数理模型から解釈するための糸口を知らされる。
以上のように、数理とくに微分方程式モデルの側から見た生物のパターン形成への研究の具体的事例が多岐に及び紹介され、生物に関した数理模型作りに多少なりとも興味を持つものにとって大変刺激的な内容といえる。章を追うにつれてマクロなレベルの観察からより生物独自の機構を取り入れた内容となる構成は、数理科学や物理学の方法論に慣れた読者には受け入れられやすい。
ただ、この手の数理模型作りに慣れないものにとって多少理解が難しい箇所もある。決して複雑でない数式もその意味をしっかり把握するには、掲載された参考文献を含めて様々な周辺知識を動員する必要がある。これは生物学と数理科学という趣向の異なる分野の相互乗り入れ可能性を手軽な一冊に押し込めようというした結果生じた避けられない「おつり」ともいえる。
生物学と数理科学の融合は今後もおそらく簡単ではない。研究手法が違うということ以上に目指す方向性が一致しないという状況がある。数理科学とくに物理学では表出する現象の普遍性に目が向かい、生物では遺伝子解析に代表されるように原因と結果の1対1対応の発見に目が向く傾向がある。生物をはじめとする複雑な現象を表層的なもの以上の模型としてしっかり表現するには、模型作りの手法そのものも注意深く検討していく必要がある。同時に、模型作りの面白さを一人でも多くの人に伝えることも重要である。
美しいガイドブックが、人々を旅行へ駆り立てるように、研究者の肉声や美しい写真を満載した本書を感性の豊かな様々な分野の(自称)若手研究者の手の届く範囲に備えておくのは悪くないと思える。
(2006年5月23日原稿受付)
R. M.バーネット,H.ミューリー,H. R.クイン著; 守谷昌代訳
クォークの不思議; 素粒子物理学の神秘と革命
シュプリンガー・フェアラーク東京,東京,2005, viii+306 p, 21.5×15 cm, 本体3,500円[学部向・一般書]
村 田 次 郎 〈立教大理〉
元素の周期律表は眺めているだけで楽しいものだ。とりわけ、文部科学省の配布する「一家に1枚周期表」は理研で発見された113番元素が掲載されていることもあり、眺める機会がこの頃特に多い。一方、素粒子の周期律表とも言うべき有名な表があり、http://www。cpepweb。org/にて入手可能だ。ヴィジュアル的にも優れたこの図表は元素の周期律表同様、ただ眺めるだけでも楽しいものだが、記載されている内容の意味をよく思い出しながら表を読んでいると少なくない知識の整理ができる優れものである。
さて、本書はこの図表を作成したCPEPという、物理教育活動を行っている非営利団体のメンバーが執筆した素粒子の入門書である。シュプリンガー・フェアクラーク東京の赤い表紙のシリーズの一冊だが、見かけによらず非常に入りやすい、 Readingsカテゴリに属する解説書である。著者らは上記の図表の解説本を意図したようだ。
本書では頭ごなしに性質を羅列する形をとらずに、数々の実験的な大発見がいかになされ、いかなる知識が獲得されたかが紹介される。このスタイルで印象的な良書はレオン・レーダーマンの「神がつくった究極の素粒子」が有名だ。こちらは大実験家である本人の経験に基づくエキサイティングな読み物だが、比較してみると本書は解説書であると同時に読み物の面も押さえたユニークな著作と言える。本書は読み物として、 J/Ψ粒子を発見した11月革命のドラマから始まり、数々の実験事実を交えながら標準模型の知識が確立されていく様子をあっけないほど簡略に説明する。加速器実験でいかに標準模型が確立されたかを解説することが主目的であることは間違いないが、宇宙物理学と素粒子物理学のつながり、そして最近の話題である重力と素粒子物理の関係なども非常に簡便に紹介している。とりわけ、大きな余剰次元に関する説明は秀逸と言えよう。
一方、本書の優れている点は充実した付録にある。検出器の動作原理、中高生程度の初等的な物理学も懇切丁寧に解説されている。もの足りない学部初年時学生らには基礎的な演習問題も用意されており、様々な用途が考えられる面白い本である。ただ、これは入門書の宿命でもあるが読み手のリズムを重視したためにあまりに大胆に論理を簡略化している一方で、解説本として広い範囲をカバーしようとしたため、初心者にとってはおよそ理解不能と思われる唐突な用語・記述の羅列が出現する部分が目立っている。あくまで冒頭の素粒子図表の解説本であるという認識にたてば、初心者は表を眺めるように流し読みでき、知識のある読者は知識を整理するためのまとめとして利用できる、ユニークな本に仕上がっていると言えるだろう。
(2006年5月16日原稿受付)
吉岡書店、京都、2005、 x+224 p、 21×14.8 cm、 本体3,200円[大学院向、学部向、一般書]
森藤正人
量子波のダイナミクス; ファインマン形式による量子力学
加 藤 岳 生 〈東大物性研〉
ファインマンの経路積分法は量子力学の一つのクライマックスともいえる重要な理論であり、近年は物性分野で使われる場面も増えてきている。しかし初学者が気軽に手に取ることのできる適当な経路積分の教科書はそれほど出版されていないように思われる。本書は量子力学のテキスト(例えばJ. J. Sakuraiの「現代の量子力学」など)での経路積分の初歩的な説明から、第一量子化の範囲内でより進んだ内容を盛り込んでいる。初学者向けのよいテキストになるのではないかという期待を胸に、本書を拝読した。
第一章から第四章までは、通常の経路積分の初歩的事項がまとめられている。第一章はブラウン運動による導入部、第二章はブラ・ケット表示の理解を前提に経路積分の導出に当てられている。第三章はWKB近似と量子・古典対応が議論される。この章は通常の教科書よりつっこんで書かれているので、初学者の参考になる部分が多い。第四章では調和振動子が取り扱われている。ブラ・ケットの説明や解析力学の説明が最低限のものとなっていることが少々残念である。
第五章と第六章で量子ダイナミクスを扱う部分が、本書の個性がもっとも表れている部分である。著者はここで量子ダイナミクスと定常状態の間の関係をさまざまな例を用いて詳細に論じている。著者は「粒子の残像」という言葉を使って、波束の時間発展からフーリエ変換を経由して定常状態を構成できることを、多くの実例を通して具体的に説明している。(この部分は経路積分がなくても議論できる。)
第七章は散乱問題を扱い、最後の第八章では波束の量子ダイナミクスを用いた半古典近似(著者は動的WKB近似と呼んでいるが、定常状態に対する手法であるのでこれは誤解を生みそうな命名である)を議論している。この最後章で、量子ダイナミクスと経路積分法の融合が果たされる。ただこの手法のメリットまでは議論されず、一つの見方の提供というレベルで止まっている。
全体を通して詳しい計算が載せられており、経路積分にまつわる計算のフォローの参考になる。また半古典理論が要領よくまとめられているので、半古典理論を使いこなしたい人が手始めに勉強するのに適している。ただ、全体としては経路積分そのものよりも、量子ダイナミクス、特にグリーン関数の時間表示とエネルギー表示の関係に力点をおいたものと言えそうである。著者の「粒子の残像」の考え方には賛否両論があるであろう。だが学部生が経路積分を自習するにあたって、気軽に手にとることのできる参考書の一つである、ということはできるだろう。
(2006年5月8日原稿受付)Basic Books, New York, 2005, 254p, 24×16 cm, $17.16[一般書]
R. B. Laughlin
A Different Universe; Reinventing Physics from the Bottom Down
福 山 秀 敏 〈東京理科大〉
著者は分数量子ホール効果に関する理論構築で1998年ノーベル物理学賞を受賞した物性物理学の研究者である。率直で気取ることなく豪放な反面大変神経細やかな大家である。本書では著者の性格そのままに「物理学」の有様についての意見表明がなされている。
本書を書くことになったきっかけは、「物理学は精神が論理的に創作するものなのか、あるいはさまざまな観測を通して醸成されるものか」(p. xii)というテーマが非専門家を交えた場でよく話題になり、しかも「何が本当か?」ではなく観念的な論争になることをしばしば経験したからだという。本書では「われわれの自然に対する理解について、それが数学的創作によるという考えと、他方経験の積み重ねによって形成されるという見方とでは基本的に異なっている」(p. xii)という認識を軸に「自然は基本にあるひとつの法則によってではなく、組織化という強力で一般性の高い規則によって規定されている」ということをさまざまな例を引きながら論証している。著者の科学に対するこのような見方はJ. Horgan1)が“End of Science"で主張した「すべての基礎はわかった、あとは詳細を調べるだけ」という「要素還元主義」(reductionism)の立場に真っ向から対立するものである。本書ではこの考え方をさらに推し進め、「すべての物理法則は集団によって規定される“all physical law we know about has collective origins"」(p. xv) と主張する。 相対論もその例外ではなかろうと言うのである。固体のように実に多数の原子の集合体においては、個々の原子を見ている限りでは想像できない「超伝導」や「量子ホール効果」が出現しそこで観測される物理量の中には物理学定数のみで表現されるものがあるという驚くべき状況が出現している。本書の主張は、このようなことは階層的に繰り返し出現するのではなかろうかという意見表明と考えられる。かなり過激なこの主張には当然さまざまな反応がある。2-4) 本書では、 加えて 「弦理論」 「量子計算」「生物学」「ナノテク」、さらには実験から離れた「理論物理」等についても辛口のコメントが述べられている。
物理学には「要素還元的」な思考形態が基本にあるのは事実であるが、一方、特定の分野でいまだに強く意識されている「科学=要素還元的思考」という考え方も非現実的である。このことが指摘されて久しい。最も古くまた明快な意見表明は1972年P. W. An-derson5) による “More is different" であろう。 この簡潔にして要を得たAndersonの「哲学的な」フレーズは当初わが国においては公開の場であまり議論されたことがなかったのではないだろうか? しかし、1994年になって金森順次郎6)がこの短いフレーズの意義を教科書で明快に論じた。Anderson7)はその後 “Emergence" という用語を用いている。この言葉は多様に使われるが、 Laughlin は本書で “physical principle of organization" (p. 6)と定義し、 また“Emergence means complex organizational structure growing out of simple rules" (p. 200)と言い、その例としてルノアールやモネの絵を挙げる:細かく見ると単なるばらばらな筆の一描きであるが距離を置いて見ると全体として明確なメッセージがあると。この主張は、大変説得力がある。実際「量の違いは質の違いとなって現れる」という数量の違いに付随する階層性の存在は自然が持つ厳粛な事実と思われる。本書はこの考えをさらに突き詰めたものである。
本書の文体は、活気に満ちている。さまざまなテーマについての説明に際して、大変豊かな学識がごく自然な形で随所にしかも唐突に表明されている。それは歴史についてであり、映画であり、また学生時代の話でもある。この類まれな精神の自由さ伸びやかさは、しばしば言及されている、カルフォリアの自然の中ですごした幼年時代の経験によるものであろう。家族に対する暖かい気持ちが至る所ににじみ出ている。実際最初の来日の際には母上と一緒であったし、別の機会に息子さんを広島に連れて行ったときのことが紹介されている。ただし、普通の日本人にはピンとこない挿入文がしばしばある。巻末のnotesは丁寧な補足説明となっている。著者との直接の議論を経験した人であれば、本書での意見表明は本心・誠意の表れそのものと理解できるが、活字だけからは「常識的」ではない大変露骨で激しい表現が第1印象となろう。しかし、内容的には棟方志功の言ったという「開けっ放しの中にいかに本当だらけが渦巻いているか」がぴったり当てはまるような印象を評者は持った。本書で主張されている事項すべてに対してすぐに賛成するかどうかは別として、現在いろいろの視点から問われている「サイエンスとは何か」について、物理学会の多くのメンバーが考えを整理したりあるいはお互いに意見交換をするきっかけとして本書は絶好であろう。なお著者によれば邦訳が準備されつつあるとのことである。
1)J. Horgan: The End of Science: Facing the Limits of Knowledge in the Twilight of the Scientific Age (Addison-Wesley, Reading, Masschusetts, 1997).
2)M. Durrani: Physics World (July, 2005) p. 11.
3)J. Ellis: Physics World (July, 2005) p. 41.
4)A. Leggett: Physics Today (October, 2005) p. 77.
5)P. W. Anderson: Science 177 (1972) 393.
6)金森順次郎:「岩波講座-現代の物理学7」固体(岩波書店,1994)まえがき。
7)P. W. Anderson: Twentieth Century Physics (IOP, 1995): 邦訳「20世紀の物理学」(丸善,1999)Chapt. 28.「20世紀の物理学についての概観」。
(2006年5月8日原稿受付)丸善,東京,2005, xii+197 p, 19.5×13.5 cm, 本体2,400円[学部向・一般書]
ジャン・ラディック著; 深川洋一訳
アインシュタイン,特殊相対論を横取りする
廣 政 直 彦 〈東海大総合教育センター〉
過激なタイトルの本書は、特殊相対論の真の創始者はポアンカレであり、アインシュタインは彼の業績を「横取り」したことを、ポアンカレとアインシュタインの特殊相対論に関する記述や、両者の人物像を比較することによって示そうとするものである。
ポアンカレが特殊相対論の創始者であるという見方は、物理学者であったE・ホイッテーカーが、1953年に著した 『エーテルと電気の理論の歴史』 で、アインシュタインはポアンカレとローレンツの理論を拡張したに過ぎないとしたことに始まる。この主張をめぐって賛否両論が戦わされており、現在でも明確な決着はついていない。本書の著者でフランスの物理学者であるジャン・ラディックは、ホイッテーカーの見解をさらに押し進めて、アインシュタインはポアンカレの相対性理論を「横取り」したと主張するのである。
ラディックは、本書の前半で時間と空間と光の概念の歴史を述べた後、第5章でポアンカレの書いた文章を引用しながら、特殊相対論の基礎を築いたのはポアンカレであることを立証しようとする。特殊相対論の形成は、独創的な仮説の提出、その仮説から導き出される数学的帰結、決定的な実験的検証の3つの段階からなっているとし、ポアンカレは1898年から1905年までの間に特殊相対論の基礎となる仮説と基本的な式をすべて発表していているので、ポアンカレが創始者であるという。続く第6章で、ポアンカレが発表した文章とアインシュタインの1905年の論文の記述を比較して、アインシュタインは何も新しいことを述べておらず、ポアンカレが長年にわたって苦労して得た成果を要領よくまとめたに過ぎないという。さらに第7章で、ポアンカレとアインシュタインの人物像を比較して、ポアンカレは家庭生活にも恵まれた謙虚で善良な人物であったのに対し、アインシュタインは家庭生活にも恵まれず野心的で恩知らずの日和見主義者であったと述べ、大学に職を得るためにポアンカレの特殊相対論を「横取り」したと主張する。
前にも述べたように、ポアンカレとアインシュタインの特殊相対論をめぐる問題には、明確な結論は出ていない。本書では、ポアンカレとアインシュタインの特殊相対論に関する記述を詳細に比較することにより、アインシュタインの述べていることはポアンカレがすでに発表していたとして、アインシュタインがポアンカレの業績を「横取りした」ことを立証しようとする。確かに、アインシュタインは、ポアンカレの著書 『科学と仮説』 などから影響を受けていることは否定できない。しかし、「横取りした」と断定するには、もう少し確かな直接的証拠を示すか、十分に納得できる論証が必要であろう。著者ラディックのアインシュタインに対する人物評価も、厳しすぎるように思える。
ところで、著者ラディックは、学生時代に特殊相対論を学んだとき、光速度一定の原理がなぜ必要なのか疑問に思ったという。その後、光速度一定の原理に基づかない特殊相対論を執筆したのがきっかけとなり本書を書くことになったのである。ラディックは、ポアンカレの相対論的な速度合成則から光速度が一定であることが導かれるので、アインシュタインの光速度一定の原理は不要であり、むしろ空間や時間の基本的な性質が、光という特別な物理現象になぜ関係しなければならないのかという疑問を生むという。そして、現在でも特殊相対論の教育は光速度一定の原理に基づいて行われており、この特権的な扱いが、特殊相対論の誕生に関してポアンカレが果たした役割をないがしろにすることになった理由であるとする。
特殊相対論の形成の問題は、その理論だけを論じるのではなく、アインシュタインの1905年の他の論文、すなわち光量子の理論やブラウン運動の理論との関係や、当時の物理学や物理学界の状況なども考慮しなければならない。本書だけではなく、科学史家の著作、たとえば我孫子誠也氏の 『アインシュタイン相対性理論の誕生』(講談社現代新書、2004年)等を合わせて読むことが必要であろう。
(2006年2月18日原稿受付)シュプリンガー・フェアラーク東京,東京,2005, xiv+230 p, 21.5×15 cm, 本体3,000円[学部向・一般書]
G.マクラッケン・P.ストット著,村岡克紀・飯吉厚夫訳
フュージョン-宇宙のエネルギー-
吉 田 善 章 〈東大新領域〉
本書は、大学教養課程の学生にとって格好の「副読本」であろう。「副読本」などというと、脇に置くような言い方で失敬だと思われるといけない。これは、評者が大学で教える者の立場で語っているためで、本書を周辺化する意図などない。むしろ優れた副読本こそ、大学生には必要だ。
本書は、フュージョン(無論、核融合のことである)を「宇宙のエネルギー」と呼んで神話化することが目的のようだ。こう言うとまた、毒のある書評だと思われるといけないので、少し説明が必要だろう。
フランスの文学者、 R.バルトに 『神話作用』 という愉快な著書がある(篠沢秀夫訳、 現代思潮新社、 1967年)。 ローマ人の髪型、ガルボの顔とヘップバーンの顔、アインシュタインの頭脳などを取り上げた軽いエッセー(カルチュラル・スタディーズ)を通じて、現代の神話を構造的に分析する。曰く「神話とは、ことばである」。それは伝達のための体系であるが、ふつうの言葉(記号)と違うのは、二重の階層的な構造をもつことだ。意味するもの(signifiant)としての言葉は、意味されるもの(signifie)と結びついて一つの意味表象を構成する。神話とは、この意味表象が signifiant に変成した「ことば」なのである。この理論に基づいて、本書の意図を分析してみよう。
前半では、アインシュタインはもちろんのこと、ケルビン卿までも動員されて、「宇宙のエネルギー」という「ことば」が定義される。太陽のエネルギーの謎を解く話はスタンダードだが、著者たちの科学史についての博識は、なかなかなものだ。ヨーロッパの研究者は、やはり重厚な歴史の上に生きている。よって「宇宙のエネルギー」は十分に響く「ことば」となっている。次に、ジョージ・トムソンがフュージョンのエネルギー利用で特許を申請したというエピソードや、さまざまな実験とか設計作業とかのルポルタージュが語られる。こうして、純粋に物理現象である核融合は、地上で究極のエネルギー源となるだろう「動力プラント」を指し示す signifiant となるのである。この神話化のプロセスは、豊富な挿絵と平易な解説で彩られて、楽しくも読みごたえがある。
私たちが大学で教えるのは、いわばヨーロッパ的啓蒙主義に貫かれた、神話の解体作業である。一方で、科学は新たな神話を作り出す。この互いに逆方向の知の営みを、ヨーロッパ人はどのように心の中で同居させるのか、そのような視点で本書を読むのも楽しかろう。広い意味で科学を志す若い人に薦めたい。
(2006年4月11日原稿受付)
NRC Press, Ottawa, 2002, viii+468 p, 15×23 cm, 10,292円[一般書]
B. Stoicheff
Gerhard Herzberg: An Illustrious Life in Science
高木光司郎
本書は、20世紀を代表する分光学者Herzbergの生涯(1904-1999)が、 丹念に記述されているという意味で、完璧ともいえる伝記である。
Herzberg.は量子力学の誕生直後に分光学の研究を始め90歳に至るまでそれを続け、数々の輝かしい業績を上げた。全3巻の大著“Molecular Spectra and Molecular Structure"は分光学者には “バイブル” と呼ばれ、 1944年に改訂版の出た「原子スペクトルと原子構造」は入門書として現在でも広く読まれている。彼は1962年の国際分光学会以来、何度も来日しているし、分子科学研究所の創設期には評議員を務めていたから、わが国でも直接に接触した研究者は少なくないだろう。
著者のStoicheffはHerzbergの研究室に所属していた、カナダの分光学者である。この本には、同研究室に所属していた岡武史氏(現シカゴ大学名誉教授)の序文があり、これが著者と本書についての格好な紹介となっているので一部を引用する。
「Stoicheffは、Herzbergより20歳年下でラマン分光と非線形分光学の開拓者として著名な学者である」「30年以上も前に先見の明あるHerzbergはStoicheffに伝記の執筆を依頼した。Herzberg は、 彼が伝記や科学の歴史の本を読むのが好きで、著述家としても優れ、細部への学者的正確さを持っていることを知っていた。彼が一個人として純粋に自分を敬愛していることも分かっていたに違いない。 Herzberg への敬愛の念と専門知識の深さと学問分野での人脈の広さは、カナダの科学政策にたいする深い洞察とあいまって、彼を理想的な伝記作者としている。先達に対する知識とその人々への愛情と尊敬の念は我々の文明の一つの支柱であり、本書は科学と人文学への偉大な貢献である」
本書を読むとこの引用がそのまま納得できる。 本文は 4 部からなり I。 若き日々(1904-1934) II。難を逃れてカナダへ(1935-1947) III。黄金時代(1948-1971) IV。晩年 (1972-1999) で、 その後に詳細な、年表、参考にした伝記、引用文献、著作リスト、各種の賞などのリスト、事項索引、人名索引がついている。
ごく簡単に内容を紹介するとI。 Herzberg。は大学入学まではハンブルグ
で育った。ダルムシュタット工科大学(THD)を卒業後、同大学で分光学の研究で工学博士となり、ゲッチンゲン大学とイギリスのブリストル大学での 1 年ずつの滞在を経て(この間に Luise 夫人と結婚)またTHDへ講師として戻ってくる。分光学者としての名声は高くなるが、夫人がユダヤ人であるためドイツで職に就けなくなり、カナダのサスカッチワン大学の物理教室に職を得る。 II。 ここで公私ともに充実した10年間をすごした後、第2次大戦後に、シカゴ大学ヤーキス天文台に移るが、3年後にカナダに戻り、オタワにある国立研究所(NRC)に赴任する。III。 NRCに分光学研究室を創設し、物理部門(1955年からは純粋物理部門)の部長に任命される。この研究室は大きく発展し、多くの優れた研究結果を産出し、世界中の研究者をひきつけ分光学のメッカと呼ばれるようになる。また優れた若者たちがポストドクとしてやってくる。65歳の定年を期に部長職から引退し、一研究員にもどる。1971年にノーベル化学賞を受賞する。 IV。受賞後の祭り騒ぎと多くの講演依頼のため研究は一時期中断する。受賞半年前にLuise夫人を亡くすが、 翌年Monika。夫人と再婚する。 再び研究に復
帰する。 1975年に NRC 内に Herzberg Institute of Astrophysicsという彼の名を冠した天体物理の研究所が作られ、分光学研究室はこの中の重要部門として位置づけられる。彼はそこで一研究員として働き、90歳で引退し、94歳で死去する。
本書の結語に。Herzberg。の科学上での主な業績としてまとめられているものは、物理では水素原子とヘリウム原子に関する仕事と水素分子、禁止遷移、前期解離についての知見。化学では多くの分子の分子構造の決定、 特にCH2、CH3、 H3のスペクトルの発見。天文学では実験室での測定に基づき星間空間中のCH+と、彗星中でのC3とH2O+の存在を明らかにし、水素分子の四重極スペクトルの観測と惑星大気中での水素の存在を明らかにしたこと。そして、あの3巻の大著の完成である。
大量な仕事を成し遂げた。Herzberg.の引き締まった生涯が一語もおろそかにせず記述され、その典拠は巻末に明記されている。学問の話はふんだんに出てくるが、同時に多くの人々との交流が語られ、写真も豊富で楽しく読める。国の研究所のあり方という議論にもかなりの頁が費やされている。
全編を貫いて著者の。Herzberg。にたいする深い愛情と尊敬の念が感ぜられ、同時にカナダ人である著者が、自国の科学に深い知識を持ちその発展を強く願っていることが感ぜられる。カナダという若い国において。Herzberg。が新し
い科学を作っていく上での大きな存在で、わが国の物理でいえば仁科芳雄とか湯川秀樹、朝永振一郎と言うような存在であったのだ、ということに私は気づかされた。なお、日本語で書かれた、より簡潔ではあるが読み応え十分の、Herzbergの素晴らしい伝記1)があることを付記する。
1)岡 武史:分光研究48 (1999) 235.
(2006年2月7日原稿受付)
東京大学出版会,東京,2005, xii+242 p, 21.5×15.5 cm, 本体3,200円(非線形・非平衡現象の数理①:三村昌泰[監修])[学部向・一般書]
蔵本由紀編
リズム現象の世界
戸 次 直 明 〈日大工〉
我々人類は20世紀前半に2つの悲惨な世界大戦を経験した。皮肉なことに、電子計算機は軍事目的のために誕生した。第二次世界大戦後、電子計算機は大学や研究所に解放された。このとき、一般の研究者が解析的に厳密解を求めることが難しい非線形現象に取り組むことが可能になったといえる。20世紀後半、電子計算機(以後Cと書く)を使って、非線形現象を「非線形波動」として捉えて「ソリトン」を発見し、また相補的に「(気象の)乱流」として捉えて「カオス」を発見したことは記憶に新しい。21世紀の現在、我々は生活空間の隅々にまで C の恩恵を受けている。今や学生は一人 1 台 C を持っている時代である。
このような時代背景のもとに、「ソリトン」 や 「カオス」 の研究で培った概念や方法論を超えて、生命現象まで含めた非線形現象の新しい展開について纏めたものが、三村先生の監修による「非線形・非平衡現象の数理」全四巻である。 本書は、「非線形・非平衡現象の数理」全四巻シリーズの第一巻で、「リズム現象の世界」 と銘打ち、 多種多様なリズム現象・同期現象に内在する普遍性について、高校生や学部学生向きに書かれた非線形科学入門書である。第1章は化学・生物世界のリズムについて、第2章は、確率共鳴というキーワードで生体のリズム同期現象を解説している。第3章は、外界のリズム刺激に対して生体が先行運動(予測力)を獲得すれば「因果律の逆転」が発生しうることが紹介されているユニークな内容である。第4章と第5章はリズム現象・同期現象の数理的基礎を解説したものであり、カオス的リズムの同期・非同期現象について、簡潔明瞭に書かれている。特に、オンオフ間欠性(変調間欠性)発現の説明は見事である。非線形振動子特有の現象である「引き込み現象」を最初に発見したホイヘンスの思想を「リズム現象・同期現象」というキーワードで現代に甦らせたものといえよう。編者である蔵本先生の「リズム・同期」へのこだわりを窺い知る本である。本書の読み方として、どうして編者がこれほどまでに「リズム・同期」にこだわるのかといった「動機」を読み取ることができれば面白いかもしれない。編者ご本人から「幼い時、原爆の光を見た」 という体験話を二十数年前に広島駅のホームでお聴きしたことがある。この体験も関係しているかもしれない。何気なくその本質を現しているような平明な言葉を使うことにおいて、編者は魔術師である。論文についても同様である。例えば、リズムの起源に関して、「エネルギーの流入と流出のバランスが失われると定常な状態は不安定になり、しばしば流れが周期的に変動することで、より高次の安定性が回復される」といった具合である。もちろん、摂動の高次の安定性をポントリャーギン風に示す場合には、多くの補題と定理の証明が必要になって、数学者以外のものには退屈になってしまう。魔術師のような巧みな表現と展開によって、リズムという現象の奥に潜む世界を楽しむことができる。とにかく、本書に出てくる数式は簡明なものばかりで初等微積分の知識さえあれば、リズム現象・同期現象に興味を持つ広範囲の一般読者(高校生や学部学生)でも読んで楽しめる本である。文系・理系を問わず、大学生の一般教養書として本書を薦める。
(2006年2月23日原稿受付)
ソフトバンクパブリッシング,東京,2005, 446 p, 15×10.5 cm, 本体900円(SB文庫)[一般書]
マーカス・チャウン著,糸川 洋訳
僕らは星のかけら; 原子をつくった魔法の炉を探して
山 本 嘉 昭 〈甲南大理工〉
本書の副題(原題:The Magic Furnace)が示すように、人間を含めて身近にあるものから太陽系、宇宙までのあらゆる物体を構成する原子が、宇宙の原初から存在するものではなく、宇宙のどこかで現在ある割合に作られたと判断されるに至った経緯を語り、原子が作られた炉を探すことを主題にした啓蒙書である。 英国の科学雑誌 New Scientistの宇宙論コンサルタントを務めるサイエンスライターの著者が日本語文庫版に寄せた前書きにあるようにまさに「手に汗握る科学推理小説」でもある。
本書は一般向け科学書であるが、登場する科学者の人柄や挿話をふんだんに取り入れて読者を誘いこむ巧みな物語であり、大学生以上のサイエンス好きの方むきである。読みどころは後半だが少し難しい箇所もある。図があれば理解しやすいと思う。科学者が慧眼を発揮して科学が発展する一方で、実験結果に驚愕したり誤った解釈や推論など、行きつ戻りつする過程をよく調べていて、時代を越えて臨場感に浸れる物語ゆえ大学院生や研究者にも一読をお勧めしたい。
19世紀から1930年代初めまでに登場する科学者は少数を除いて、偏りを感じるほど英独仏3国であるのは西欧の伝統の奥深さであり、今更ながら驚く。
本書は3部からなり、第1部ではすべてのものは原子からなり、さらにその奥に原子核の存在を知るに至る過程が丁寧になぞられている。
第2部では、スペクトル線から太陽に様々な原子の存在を見出したあと、20世紀の科学者にとっての大問題 “太陽や星が輝き続けているそのエネルギー源はいったい何か” を探る現場に読者を誘い込み、徐々に解き明かしていくが、少しくどく感じる。
第3部で解明されるが、星は鉄の原子で均質にできていると信じたエディントンは、エネルギー源を別にして星の明るさや色はすべて説明できる。だが、太陽の数千倍も明るい赤色巨星の周縁部が大きく膨らんでいるのは説明困難だとか、ラザフォードが星のエネルギー源が放射性元素のアルファ崩壊であり、それゆえに太陽にヘリウムがあると考えるくだりは、いろいろな意味で教訓的であるが、ほっとする。
第3部では、宇宙の元素は大部分が水素であり、ベーテやヴァイツゼッカーらにより星の炉で水素が核融合してエネルギーを出すこと、次々と重い元素が合成されて鉄に至るが、それ以上は赤色巨星や超新星爆発に魔法の炉があり、ヘリウムなど軽元素はビッグバン初期の炉で作られ、生命に必要な炭素と酸素の星の炉での微妙な合成割合が語り解かれる。
著者は訳者の電子メールに答えて、1983年のノーベル賞はファウラーと一緒にホイルも受賞していて当然だったと、ホイルに肩入れしている。フレッド・ホイルの言い分がまた奮っている。パルサーに関する1974年のノーベル賞は発見者の大学院生ベル嬢がはずれ、指導教官に与えられたのでノーベル賞委員会を批判したからだと。
(2006年1月30日原稿受付)
東京大学出版会、東京、2005、 xvi+249 p、 19.5×13.8 cm、 2,800円[一般書]
川島慶子
エミリー・デュ・シャトレとマリー・ラヴワジエ; 18世紀フランスのジェンダーと科学
八 木 江 里 〈八木江里科学史研究所、NPO学術研究ネット所属〉
本書は18世紀を代表するフランスの “才女” の科学への大きな寄与を綿密な資料調査にもとづき時代背景とともに記述した興味深い読み物である。
川島慶子氏は、国際的にも活躍中のジェンダー研究第一人者の一人。
私は2005年7月、北京国際科学史会議でジェンダー関係の研究として、日本物理学会で「国立大学に女性の物理の教授を増やそう!」と活動してきた過去20年の歴史分析を報告、加えて、ほぼ全てのジェンダー関係の集まり(Women in Science and Technologyのシムポジウム、セクシオン、コミッシオン) に参加してきた。 (ここでジェンダーとは社会的な性差を意味する)。
またかつて参加した1985年のバークレイでの国際会議では、今後はマリー・キュリーとその関連のことだけでなく、広く様々な時代、国、分野における女性達についての多角的な調査、研究が必要だとの意見が出ていたことも記憶している。私のような実戦的ジェンダー研究者の側面を持つ者の立場からこの労作を紹介してみたい。
ほとんどの人が、今までの出版物からエミリー・デュ・シャトレ(1706-1749)はフランスにニュートンの 『プリンキピア』 を仏訳して紹介した女性、マリー・ラヴワジエ(1758-1836)は元素表を最初に作り、ギロチンに消えた悲劇の化学者ラヴワジエの夫人かつ協力者であつたとの、それぞれについての理解は持ち合わせていると思われる。しかしながら、ジェンダー的な視点から2人を取り上げて、比較研究した著作はほとんど存在していない。そこにこの本の意義がある。
対話形式で書かれた作品は、よく知られているガリレオの著作等もあり、珍しくはなかつた。とは言え、フォントネルがデカルトの宇宙論を紹介した 『世界の複数性についての対話』(1686初版後ベストセラー)で女性を初めて登場させていることが重要であり “貴婦人たちを科学の観客、パトロンに” という彼の意図を超えて、これら “才女” のような実質的な “参加者” を生み出したと言う。
川島慶子氏は、『物理学教程』(1737年頃からはじめ1740年に出版)と「火の本性と伝搬に関する論考」(科学アカデミー懸賞論文の次点としてその雑誌に掲載)の執筆、と出版とに示されたエミリー・デュ・シャトレの態度が、当時の科学界で女性が置かれていた弱い立場をなまなましく反映していると力説している:即ち男性に比較していろいろと不自由な面が多く、批判の対象にはなるが、正当な評価の対象にはなりにくい状況がそこにはあった。エミリー自身は男性と同様な「考える生き物」であるとの自覚と自信をもって当時の発見を網羅する教科書として 『物理学教程』 を執筆したのだと言う。
エミリーが 『プリンキピア』 をラテン語から仏訳する作業にとりかかったのは、1745年頃で、すでに高く評価されていたニュートンの著作を仏訳することで、彼女自身も、「同時代人よりも公正である後世の賞賛」を求めていたと言う。数学者クレローの学問的な協力と、長年の恋人であつた男友達ヴォルテールの理解に支えられて、1749年9月の出産直前までに彼女自身の注を含む草稿を完成させた。そしてエミリーは、若き恋人、サン・ランベール侯爵との間の子供を出産後、不幸にして、たった6日で(母子とも)亡くなってしまう。
マリー・ラヴワジエについては、夫や父、兄弟である男性学者の「見えざる助手」であつた女性の立場の持つ意味についての考察がなされている。何故なら当時でも現在でもそういう協力は賞賛されるものの、彼女達自身がこの役割を選んだ動機が真剣に討議されたことはなかったからだと川島氏は言う。この動機には、その男性に対する愛とか尊敬とかの女性の特性にあるという世間的(男性的)解釈が存在しているだけであると言う。川島氏はマリー・ラヴワジエもまたその学問に精通したいと願い「そこに自分の価値を預け、自分を開放してくれる何かを、新化学の推進活動に見出しうると信じたのだ」と書いている。科学史に偉大な足跡を残した男性に協力した女性として名を残したラヴワジエ夫人の立場の方が、現在の科学史研究の現場からでも、ジェンダー問題の存在を鮮明にしてくれると川島氏は述べている。
最近、日本物理学会でも男女共同参画推進のための委員会ができて、私もネット・コメンテーターとして参加させていただいております。女子高校生達への科学(物理)の関心度を高めようとする夏の催しも成功裡に実行されました。しかし建前としては「社会における役割分担は男女の差別によらずに行おう!」と言うのですが、まだまだ男性中心的な意識が社会一般の至る所に存在しております。さる9月11日の衆議院議員選挙で多数の女性議員が誕生して、国会議員の10%を女性が占めることになりました。社会意識の “変革” が期待されております。 この労作は、将来の科学とジェンダーのあり方に関心を持つ方々に有益な示唆を与えてくれることでしょう。
(2005年11月4日原稿受付)
岩波書店、東京、2005、 xx+363 p+30 p、 19.5×13.5 cm、 本体3,000円[一般書]
P. C.アイヘンブルク、R. U.ゼクスル編; 江沢 洋、亀井 理、林 憲二訳
アインシュタイン; 物理学・哲学・政治への影響
安孫子誠也 〈聖隷クリストファー大〉
原書は、1979年にアインシュタイン生誕100周年を記念してVieweg社からドイツ語版と英語版が同時出版された。同年に、岩波現代選書の一冊として邦訳出版されたものが、1905年から 100 周年の「世界物理年」を機に、 今回単行本として再出版されたのである。
15名の執筆者の中に、我が江沢洋氏が含まれていることは、誇らしい気持にさせてくれる。最初の4編は宇宙論・ブラックホールなどの話題に捧げられ、続いて量子力学・統計力学・特殊相対性理論・科学哲学への貢献が論じられる。終わりの5編では、思想的・政治的なものやアインシュタインの思い出など、種々雑多な話題が取り上げられている。
大勢の論者が、あらゆる角度からアインシュタインを論じ、貢献の全貌を明らかにしてくれることが本書の特長である。しかし、出版が1979年であることに伴う共通の弱点もある。というのは、 1987年からThe Collected Papers of Albert Einsteinが出版され始め、それに基づき多くのアインシュタイン研究が積み重ねられたにもかかわらず、その成果が盛り込まれていないからである。ただし、出版以後の物理学上の研究成果については、「新版にあたって」の中で補われている。
内容上、気になった点をいくつか指摘する。 p。 121に、 「プランクは、 振動数νの輻射はhνだけの…『量子』 として放出されたり吸収されたりするものと仮定して」とあるが、筆者の理解では、それを仮定したのはプランクではなくアインシュタインである。 またp。 152 に、 「ローレンツが…数学的補助仮説とみなした 『局所時間座標』 を、時間そのものとみなすべきではないかという考えが、1905年をまえにして頭に浮かんだとアインシュタインは後に書いている」とあるが、引用符の文献にそうは書いてない。著者ミラーの誤読が疑われる。 さらにp。 154には、 特殊相対論が、ローレンツ電子論を基としたアインシュタインの発想の転換によってもたらされたと示唆する記述が見られるが、最近の研究に照らせば、この見解は修正されるべきである。
翻訳についても気になった点がいくつかあった。「4。重力波」で、原書のFig。 5(J。 Weberの論文)が、 理由も示さず省かれている。p。 36の「輻射(原書はlight)」は、 「重力輻射」と「光」のどちらなのか分からない。 p。 61の「外側の枠(an aspect)」は、 「一側面」とすべき。p。 217の「ちらつき(Zitterbewebung、 fluctuation)」は、「揺らぎ」とすべき。p。 255の「こんな膨大な経験事実の集積から(No ever so inclusive collection of empirical facts)」 は、「いくら完璧に経験事実を集積しても」とすべき。「16。」の副題「学者の世界の周辺(and the Vanity of Academia)」で、vanity(虚飾)を「周辺」と訳すのはいかがなものか。
(2005年11月21日原稿受付)裳華房、東京、2005、 x+146 p、 19×12.5 cm、 本体1,600円(ポピュラー・サイエンス271)[一般書]
嶺重 慎
ブラックホール天文学入門
吉 田 健 二 〈神奈川大工〉
本書は、天文学者の立場から初心者に向けて、ブラックホールに関する課題に興味を持ってもらいたいと書かれた一般書である。著者は理論を専門とするブラックホール天文学研究の第一人者である。
内容は、第1章のブラックホール発見の歴史的経緯に始まり、第2章では近接連星系の恒星質量ブラックホールから銀河中心の大質量ブラックホールにいたる様々なブラックホール天体の説明がなされている。第3章から第5章ではブラックホールの周りの降着円盤、第6章ではブラックホール近傍から吹き出す高速ガスの流れ(ジェット)、第7章ではブラックホールの形成と進化について、それぞれ最新の理論モデルと電波・可視光・X 線による観測結果を紹介しながら説明を行っている。第8章では将来のブラックホール観測方法として、重力波による観測方法、重力マイクロレンズや大型の電波干渉計を用いる方法を紹介している。
特に本書では、どのように研究者同士の論争が行われ、どのように研究が発展してきたのかということが生き生きと描かれており、「ブラックホール天文学」の最先端の研究トピックスとともに研究の経過も知ることができるようになっている。また閑話として掲載された6つのコラムには、研究者として著者の印象に残った話題や研究する上での心構えが記されており、読者にとっても印象深いものになっている。ただ、「数式を見ると読む気をなくす」という人のために本文中ではできる限り数式を省いた、というまえがきの記述に反して、本文中に不用意に数式が用いられている点が気になった。
本書は、テンソル記号に埋め尽くされるようなブラックホールの物理を説明することに焦点を当てていない。ブラックホールの強い重力場がどのように面白くも激しい宇宙現象を引き起こしているのか、ということを説明することに焦点を当てている。また本書では、著者の専門とする理論的側面だけでなく、X 線観測などの観測的側面についても十分な紹介がなされている。本書を読むことによって、ブラックホールがその背後に潜むような様々な宇宙の物理現象-宇宙ジェット、爆発現象、磁気活動など-について知ることができるであろう。特に、降着円盤に関しては詳細に説明がなされており、ブラックホール降着円盤学への格好の入門書ともなっている。
(2006年1月10日原稿受付)
Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, 2005, 24×16 cm, xxii+693 p., 16,780円[一般書]
D. Bodansky
Nuclear Energy; Principles, Practices, and Prospects
小 川 雅 生 〈東工大原子炉工学研〉
この本は原子力を専門としない人を対象としており、原子力に関わる諸問題を広範囲に解説している。興味のある人は、是非、チェルノブイリ事故の章だけでも読んでみることを勧めたい。本書はまた、原子力を専門とする人にも、原子力の全体像を再確認する意味で勧めたいと思う本である。すなわち、原子力ありきの、原子力推進を前提とした原子力教科書ではなく、著者は原子力を幾つかあるエネルギー源の一つのオプションとして捉え、原子力発電を公平・中立な立場から記述している。
原子力の重要な課題の一つは安全性であり、原子力発電所におけるリスク解析を幾つか紹介している。一例として 米 国 NRC(National Regulatory Commission、 原子力規制委員会)に提案されたが採用されなかった炉心損傷率 10-4/炉年の場合、 世界中に 4、000 基の原発が稼働する時代には、 TMI炉(Three Mile Island炉)型の事故が2~3年に1回起きることになり、これでは社会に受け容れてもらえないが、炉心損傷率が10-6/炉年~10-5/炉年ならば受け容れてもらえるだろうと述べている。航空機や自動車の事故に比べて、原子力事故は厳しく受け取られるが、過去の原子炉事故の経験がリスク解析の妥当性を判断するものと考えられる。
原子力発電は原子力の平和利用であるが、ウラン濃縮技術と燃料再処理技術は軍事利用に転用されやすい面があるとし、原子炉に加えて核兵器(水爆を除く)を解説している。最近の国際テロ活動に言及し、濃縮ウランやプルトニウムの核拡散問題を技術面から述べている。濃縮ウランはγ線をほとんど出さないので、空港等での検出が不可能に近い。他方、プルトニウムの場合、中性子放出数が多いので検出は簡単である。核保有国の拡大を防ぐ手段として、 NPT(Non-Proliferation Treaty、 核兵器不拡散条約)やCTBT(Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty、 包括的核兵器実験禁止条約)に触れている。
全体を通して、私が面白いと思った事項は以下のものである。
・原子炉発展の歴史
・過去の原子炉事故例
・原子力の将来展望
・チェルノブイリ事故が発生した経緯を炉物理の視点から説明していること
・臨界質量を、反射体なしとありの場合について提示していること
・中国は1964年の最初の核実験から爆縮型ウラン爆弾であったこと
・しかし、発電はずっと遅れて30年後の1994年であること
・パキスタンの1998年の核実験は小型爆縮型ウラン爆弾であり、遠心法で濃縮ウランを作るハイテク型であったこと
・米国の核廃棄物貯蔵計画は50年分の7万トンであり、ユッカマウンテンをサイトとして選定した理由が詳しく解説されていること
なお、本書は中性子物理や原子炉の仕組みに関する記述が少ないので、原子力専門コースで原子炉物理あるいは原子力工学を教えるための教科書ではない。しかし、本書を参考にして、中性子増倍係数kがk≫1の領域である核兵器やk>1となったチェルノブイリ事故を解説すれば、学生の興味をひきつけ、k=1の条件で運転される原子炉の仕組みを理解させるため役立つであろう。
(2005年9月13日原稿受付)
Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg, 2005, viii+222 p., 24×16 cm, \6,280[一般書]
A. Noess
Galileo Galilei-When the World Stood Still
田 中 一 郎 〈金沢大〉ガリレオ・ガリレイのように何世紀にもわたって研究が続けられてきただけでなく,最近になっても評伝が書き継がれている科学者はまれかもしれない。こうした理由から独自色を出すため に、 Sobel の Galileo's Daughter (Fourth Estate、 London、 1999; 邦訳は 『ガリレオの娘』、DHC、 2002年)はガリレオを正面から取り上げることなく、娘の視点を借りることで彼の半生を新たに描いたのかもしれない。本書の場合、小説とはいえ、この間の研究の成果を取り入れることでガリレオの本格的な伝記を目指している。かつての伝記を彩っていたピサのランプや斜塔の逸話が影を潜めているのも、こうした意図と関係しているのだろう。ただし、ガリレオの異端審問所への召喚と三十年戦争末期の政治的混乱とを重ね合わせることから書き始めている事実に示されるように、十七世紀前半の政治状況の中で彼の生涯を再解釈しようという意図は明らかである。
こうした印象をさらに確かなものにしているのは、ガリレオ裁判の記述を教皇庁におけるウルバヌス八世とスペインの枢機卿との対立から説き起こしていることである。それに続いて、ウルビーノ公国を巡る教皇とトスカナ大公国との確執が述べられる。複雑な政治の渦中にガリレオもウルバヌスもいたのであり、そうした視点からの裁判解釈はあってしかるべきだろう。
たとえば、ガリレオの父親についての記述など、研究書であれば避けたであろういくつかの踏み込んだ解釈は、小説であれば許されるのかもしれない。気懸かりなのは、引用と出典の多くが、FantoliのGalileo (Vatican City、 1996)だということである。ガリレオ裁判の「再審」 の後で書かれ、 しかもヴァチカン天文台出版局(カトリックの科学的問題の権威と考えてよい)から出版されたFantoliの著書がヴァチカン公認のガリレオ研究書だとすると、極端な言い方をすれば、本書のほうはいわばヴァチカン風ガリレオ小説といったところだろうか。それはそれで一つの伝記であり、本書が特色あるガリレオ伝ということを否定するものではない。
(2005年10月11日原稿受付)
ページの頭に戻る