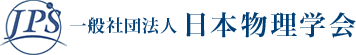会誌Vol.79(2024)「新著紹介」より
このページでは、物理学会誌「新著紹介」の欄より、一部を、紹介者のご了解の上で転載しています。ただし、転載にあたって多少の変更が加わっている場合もあります。また、価格等は掲載時のもので、変動があり得ます。
工学系のためのレーザー物理入門
三沢和彦,芦原 聡
講談社,東京,2020,viii+245p,21 cm×15 cm,3,960円[専門~学部向]ISBN 978-4-06-153281-6
紹介者:渡邉紳一〈慶應大理工〉
本書は「工学系のための」という枕言葉がついたレーザー物理入門の教科書である.たしかに第1章の「レーザー光の応用」では,工学的に重要な技術(レーザー顕微鏡,光ファイバー通信,光記録,レーザー加工など)を概説している.しかしながら,第2章以降では本格的なレーザー物理学の基礎を展開しており,工学系だけではなく,理学系の学生や研究者にとっても有用な一冊である.
本書の特長は,「はじめに」で触れられているように,コヒーレンス(可干渉性)を基軸として多くの光学現象を説明していることである.第2章の「レーザー光の性質」の部分は特に優れている.ここでは,時間,空間,周波数のコヒーレンスがすべて揃った理想的な条件下で,レーザー光の指向性,集束性(これらは光の空間波面形成に関連),および高速性(超短パルス光の時間波形に関連)について,光電場の空間,時間,周波数分布を数学的に表現しながら詳しく説明している.特に印象的だったのは,レーザー光を使用する際に実用的に重要なガウスビームの空間波面形成について,遠くに飛ばした時,凸レンズで絞った時,共振器に閉じ込めた時など,様々な状況に対応して丁寧に数式を導出している点である.ガウスビームの空間波面形成については,ヤリーヴ・イェーの教科書『光エレクトロニクス』の記述が有名だが,それと比べても,本書はより実用的に重要な部分に焦点を当て,簡潔だが詳細な説明をしていると感じた.
第3章の「レーザーの原理」では,はじめに正帰還の概念を簡単に紹介した後に,レーザー発振の原理についてレート方程式を用いて説明する.その上で,レート方程式を二準位原子と光の相互作用の視点から量子論へと拡張することを試みる.通常,この部分は密度行列を用いた光学的ブロッホ方程式を用いて説明することが一般的だが,本書では密度行列の概念を導入せず,反転分布と分極の要素を抜き出して,基礎方程式を丁寧に記述する方法を採用している.これは初学者にとって理解しやすい形式だろう.一方で,本書は入門書であることから,レーザー発振の量子論をより深く学びたい読者にとっては,他の参考書で補足する必要があるとも感じた.さらに,この章の最後には,様々なモード同期パルスレーザーの歴史,原理,特徴が説明されている.これは最新のパルスレーザー技術を学びたい読者にとって有用なガイドとなるだろう.
第4章の「媒質中の光の伝搬と非線形光学効果」では,物質内の非線形光学現象が幅広く説明されている.振動子ポテンシャルの非調和性や位相整合など,基本的事項の説明を組み込みつつ,様々な非線形光学現象が説明されている.疑似位相整合,白色光生成による自己位相変調効果,非線形ラマン散乱など,現役の研究者にも有用な内容が豊富に含まれていて参考になる.内容は多岐にわたり,限られたページ数の中で,これほど多くの内容が含まれていることに感銘を受けた.また,代表的な二次非線形光学材料の特性が表形式でまとめられている点も,実用的に価値が高いと考える.
なお本書は,「読者を意識すること」を念頭に様々な配慮がなされている.例えば,面倒な式変形も途中の式変形をほぼ省かずに記載してあり,読者が道に迷うことは少ない.また,光電場について正弦波表示で書いているのか複素表示で書いているのかを混乱することもない.さらに,変数の添え字も整理されており,非線形光学現象の教科書に特有な煩雑な添え字に伴う圧迫感を感じない.総じて読みやすく,初学者が入門書として読むことに限らず,ベテランの研究者がレーザー物理の基礎を素早く復習するときにも役立つだろう.
(2023年5月29日原稿受付)
超伝導;直観的に理解する基礎から物質まで
小池洋二
内田老鶴圃,東京,2022,xi+364p,21 cm×15 cm,5,500円(物質・材料テキストシリーズ)[専門~学部向]ISBN 978-4-67536-2319-8
紹介者:吉澤俊介〈物材機構〉
超伝導体を研究する実験系の研究室にいた学生のころ,初めて参加した物理学会で,超伝導関係のセッションを聴講したものの,知らない単語がつぎつぎに登場してあまり理解できなかった思い出がある.不勉強を白状するようだが,超伝導物質の種類も,超伝導体で起こる現象も,それらを研究する手段も多種多様なので,自分の研究の周辺だけ勉強しても予備知識として全く足りないことを痛感した.しかしその予備知識を得ようにも,入門的な教科書で扱われる内容と研究の最前線で飛び交う話題との間には大きなギャップがある.そのギャップを埋めるには個別の論文や解説記事で学んだら良いが,実験系の学生には難しい内容のものも多い.もし当時,超伝導の基礎事項から始めて分野全体を見通しよく学べる教科書があったら,どんなに助かっただろうか.
本書は,超伝導の実験系の研究室に配属された学部4年生や修士の学生が,超伝導の考え方と(物性物理学分野で行われるような)超伝導研究の全体像がつかめることを意図して書かれた教科書である.『新著紹介』欄でも何度か取り上げられている内田老鶴圃の物質・材料テキストシリーズの一つとして出版されている.学部レベルの量子力学,熱・統計力学,初歩的な固体物理の知識は前提とされているが,随所で補足があるので,多少うろ覚えでも思い出しながら読み進められるだろう.
本書は全7章から構成される.第1章で対凝縮状態としての超伝導の短い導入があり,第2章で完全導電性,完全反磁性,磁束の量子化という超伝導を特徴付ける3つの現象が示される.第3章では比熱,準粒子トンネル現象,ジョセフソン効果など,超伝導体の一般的な性質が紹介される.第4章では現象論を扱っており,ロンドン理論やギンツブルグ・ランダウ理論が導入される.第5章は微視的理論の章である.その前半はBCS理論の解説になるが,第二量子化法を用いた計算はほぼ省かれている.第5章後半からは本書の特色が強くなる.強結合超伝導とBCS-BECクロスオーバーの説明があり,さらに異方的電子対とその形成機構としてのスピンゆらぎと軌道ゆらぎが紹介される.第6章は,160ページにもわたる各種超伝導物質のレビューになっている.取り上げられている超伝導物質は,元素単体から始まり,合金,2元化合物,2次元超伝導体(遷移金属ダイカルコゲナイドやボロカーバイド,MgB2など),1次元超伝導体,有機超伝導体,磁性超伝導体,重い電子系(空間反転対称性のない化合物を含む),酸化物,銅酸化物,C60インターカレーション化合物,鉄系超伝導体,BiS2系超伝導体,超高圧下の水素化物に及び,バルク物質に関しては網羅的に近い.銅酸化物超伝導体と鉄系超伝導体については,当然ながら,他より多くのページを使って解説されている.なお,トポロジカル超伝導体や表面・界面の2次元超伝導については,省略されているか,軽く触れられている程度である.最後の第7章では,常圧・室温超伝導を実現する方策に想像を巡らせて締めくくられる.
本書の特徴は大きく3つ挙げられる.第1に,タイトルに「直観的」とあるように,超伝導体の性質を理解するための考え方を平易な言葉で説明することに重点が置かれている点である.実験データの当てはめにも使うような基本的な関係式は導出されるが,進んだ内容についてはアイデアの定性的な説明が主となる.数式に目を回す心配はあまりないが,理論系の人が読むと物足りなく感じられるかもしれない.第2に,脚注の多さである.ほとんどすべてのページに脚注が付いており,ページによっては面積の半分以上が脚注で占められている.ここでは,本文に入りきらない議論の補足,超伝導の話題に登場しがちな周辺知識,超伝導体が発見されるに至った経緯などが,やや小さめのフォントでびっしり紹介されている.第3に,超伝導の初歩から,各種超伝導物質で対形成機構がどう理解されているかまで,連続して学べる構成になっていることである.これらの特徴により,本書は1冊の教科書としては相当多くの話題が噛み砕いた説明とともに盛り込まれている.読み通せば最新の研究で頻出する物質や概念と(おそらく最速で)一通り顔見知りになれるだろう.一方,厳密な説明を省いている部分も多いので,もっと正確に理解したい時には,巻末に紹介されている発展的な教科書などを必要に応じて参照すると良いかもしれない.
以上をまとめると,超伝導の(とくに実験系の)研究を始める学生や若手研究者にとって,本書は基本事項から最近の研究までカバーする心強いガイドブックになるだろう.通読するのも良いし,すぐ手に取れる所に置いておくのもおすすめである.ちなみに某ECサイトのレビューには文字が小さくて辛いという指摘があるが,想定読者は若手なのであまり支障はないと思われる.
(2023年6月5日原稿受付)
放射線物理学
C. Rangacharyulu 著,遠藤 暁・和田義親 訳
森北出版,東京,2022,ix+262p,22 cm×16 cm,4,400円[大学院・学部向]ISBN 978-4-627-15751-4
紹介者:間嶋拓也〈京大院工〉
放射線物理学の教科書を探すと,医療技術者向けの国家試験に対応したものが多く見つかる.また,原発事故による社会的な関心の高まりにより,一般向けの関連書籍も増えた.その一方で,放射線や量子ビームの関連分野は上記以外にも幅広く多岐にわたるが,これらの研究者・技術者に適した学術的な入門書は少ない.
初等的な入門書の多くは,「放射線とは何か?」から始まり,ボーアモデルに続く原子構造や原子核の基本など,放射線物理の前提となる基礎知識の説明に多くのページが割かれる.これに対し,本書も非専門家向けではあるが,「必要とされるのは学部1年生での数学と物理の知識」とあって,原子の説明から始まることはない.準備の章は1章のみで,書籍の前半で放射線の発生や物質との相互作用の説明がなされる.後半では線量測定や発生装置,検出器などの技術的な解説がなされ,最後に放射線技術の応用例が物理過程と関連付けて紹介されている. 放射線と一言でいっても荷電粒子,電磁波,中性子で相互作用の仕方が異なるため押さえるべき範囲はそれなりに広い.これらの物理を本当に理解するには,高度な電磁気学や量子力学の知識が必要であり,非専門家向けの"放射線物理学"の範囲を超える.本書は,各項目の導入部と結論の説明に重点を置くことにより,全体をコンパクトに収めている.
原著には「Concepts, Techniques and Applications」の副題がある.物理学者である著者が,物理的なコンセプトに気を配りつつ説明が進むのが本書の特徴である.例えば,1章では最初に保存則の要点が語られており,物理志向の読者は共感を覚えるだろう.3章では「原子核には,崩壊するものと崩壊しないものがあるのはなぜだろうか」という問いかけが始めにあり,ひとまず「最も単純な答えはエネルギー収支である」というコンセプトが示される.5章の序文でも「物質と光子の相互作用では,エネルギー損失ではなく,光子ビームの強度の減弱について考える」と述べられ,荷電粒子の場合とのコンセプトの違いに気付かせてくれる.
本書のもう一つの大きな特徴は,例題や演習問題がふんだんに織り込まれている点である.具体的な計算によって理解を深める仕掛けとなっており,教育現場でも活用が期待できる.また,基礎データを調べるための実用的なウェブサイトも紹介されており,現場の研究者・技術者を意識して書かれていることが伺える.
重荷電粒子と物質の相互作用の章では,細部で気になる点があったので,僭越ながら言及してみたい.ベーテの式に出てくる「平均励起エネルギー」あるいは「平均励起ポテンシャル」と一般に呼ばれる量が「イオン化ポテンシャル」とされているのには違和感があった.また,物質中でのイオン価数が入射時の価数で制御できるように読めてしまうところも少し引っかかった.α粒子が空気中を透過する際の,単位長さあたりのエネルギー損失を示すグラフ(いわゆるブラッグ曲線)も値や形状が不自然で,何か取り違いがあったのではと想像する.前述のとおり放射線物理学の扱う範囲は広く,単独で全てをまとめるのは非常に困難な仕事である.紹介者も馴染みのある箇所以外の詳細はわからない.いずれにしても,深掘りしたい項目のある読者は,本書を入口にさらに専門的な文献に当たってその理解を深めることになるのだろう.
本書は,全体を俯瞰しながら放射線物理の物理的な要点を学べる貴重な本となっている.読者に語りかけるような筆致で,翻訳も読みやすい.これから放射線物理を専門にしようとする学部生の入門書としてはもちろんのこと,放射線や量子ビームに携わる多様な分野の研究者,技術者,大学院生らが,その物理過程をしっかり理解したいと思ったときの手引きとしても,有用な一冊である.
(2023年6月12日原稿受付)
思考実験 科学が生まれるとき
榛葉 豊 著
講談社,東京,2022,246p,18 cm×11 cm,1,100円(ブルーバックス-B2193)[一般向]ISBN 978-4-06-527068-4
紹介者:村山 功〈静岡大院教育〉
ガリレオ・ガリレイの『新科学対話』では,重い物の方が軽い物より早く落ちるというアリストテレスの主張を支持するシムプリチオと,以下の対話が行われる.
サルヴィヤチ「ではもし自然速度の異なる二つの物体をとって,二つを結び合わせた場合,速い方の物体は遅い方の物体のために幾分かその速さを緩められ,遅い方は速い方のため幾分か速められるということがあるわけですね.こういう考えでは私と一致するでしょうか.」
シムプリチオ「全く仰せの通りです.」
サルヴィヤチ「しかし,もしこれが本当だとし,そしてもし大きな石が例えば8の速さ,一方小さな方の石が4の速さで動くとすればその二つが結び合わさったものは8より小なる速さで動くでしょう.ですが二つの石が結合されれば,その大きさは,以前8の速さで動いていた石よりも大となりますから,重い物体が軽い物体よりも速度が小であるという,貴方の仮説と全く相反する結果になります.これで貴方の仮定,即ち重い物体が軽い物体より速度が大きいということから理を推して行けば,重い方が軽い方より一層速度が小さくなる,と言えることがお分かりでしょう.」
(今野武雄・日田節次訳『新科学対話(上)』岩波書店pp. 97-98,筆者により表記を変更)
この話を初めて知ったとき,私はその鮮やかさに感動した.今これを書いていても,その気持ちは変わらない.同じ思いの読者も多いのではないだろうか.
本書は「思考実験」について論じた書籍である.「第1章 思考実験を始める前に」で仮説の生成について論じた後,次の「第2章 実験とはなんだろうか」において,まず思考がとれた「実験」から考察を始めている.実験とは仮説から演繹される結論と実験結果から演繹される結論とを闘わせるものであり,思考実験はこの実験を実際に行わずに頭の中の操作から演繹するものというのが著者の主張である.この,仮説,演繹,結論の組み合わせを思考実験のセオリーと呼んでいる.そのあとで実験しない実験として自然実験や計算機実験などを取り上げ,思考実験との違いを論じている.こうして,思考実験を原理や法則を求めるために行われるものとして位置づけ,次章からその説明に入っていく.ただし,原理や法則を求めるといっても,それを生み出す手段というよりはふるいにかける手段として扱われている.
「第3章 思考実験の進め方」では,アインシュタインの自由落下するエレベーターとマックスウェルの悪魔を例に取り上げ,それを第2章で示した思考実験のセオリーで説明していく.思考実験の例を示し,そこで検討される仮説を明示し,仮説から演繹的に導かれる結論と思考実験から操作的に導かれる結論を対比することで,その思考実験の仕組みが示されていく.この記述方法は,これ以降の章でも一貫して用いられている.これに続いて,テセウスの船を例にして物理学以外での思考実験について議論を展開している.これは著者が思考実験を科学の方法としてだけではなく,人がものを考え意思決定していく方法だと捉えているからである.
「第4章 思考実験の分類」では,ポパーの挙げた「批判のための思考実験」,「発見のための思考実験」,「弁護のための思考実験」の3タイプに加え,「問題提起のための思考実験」,「判断や解釈のための思考実験」,「教育的な思考実験」の合計6タイプを提唱している.第5章以降は,このうち5つのタイプの思考実験について順に解説していくが,残念ながら発見のための思考実験は取り上げられていない.発見のための思考実験は,思いつきを理論化するために,それがうまくいくかどうかを確認するためのものであり,第3章で触れたアインシュタインの自由落下するエレベーターがその典型例だとしている.これを詳述しない理由は,「ほかのタイプの思考実験の前段階であり,やや趣が異なりますので」としか書かれておらず,期待も大きいだけに少々納得し難い.
「第5章 批判と弁護のための思考実験」「第6章 問題提起のための思考実験」では,不確定性原理に関する思考実験や,シュレーディンガーの猫,アインシュタイン=ポドルスキー=ローゼンのパラドックスなど,量子力学に関連した有名な思考実験を紹介しながら話を進めていく.しかし,「第7章 判断や解釈のための思考実験」になると,一転してマイケル・サンデルのトロッコ問題やチューリング・テストなど科学から離れた思考実験を題材とし,原理や法則が成り立つかどうかではなく複数の考え方を比較検討するような思考実験について論じている.
「第8章 教育的な思考実験」では,ある理論を学習してもどうにも腑に落ちないとき,「最低限の本質を頭の中で自分の思うままに動かしてみて,そうなることを確信するために役立つのが思考実験」だと解説されている.そして,最後の「第9章 意思決定と思考実験」で意思決定理論と思考実験を結びつけて,人生において思考実験が持つ意義にまで話を広げて終わっている.
1986年に同じブルーバックスから刊行された金子務著『思考実験とはなにか』は,自然科学の思考実験だけを扱ったエピソード重視の内容であった.これに対し本書は,科学以外の思考実験も幅広く扱いながら,思考実験の仕組みや役割について迫ろうとしている.これは,金子氏が科学思想史を専門にしているのに対し,本書の著者が科学哲学者であることからくる違いだと思われる.両書を読み比べると本書の持つ面白さがさらに際立つのではないだろうか.
(2023年1月25日原稿受付)
入門 現代の宇宙論;インフレーションから暗黒エネルギーまで
辻川信二 著
講談社,東京,2022,ix+253p,21 cm×15 cm,3,520円[大学院・学部向]ISBN 978-4-06-526631-1
紹介者:樽家篤史〈京大基研〉
題名が示す通り,本書は現代宇宙論,英語でいうphysical cosmologyの内容をまとめた専門書である.宇宙の成り立ちとその進化を探る宇宙論は,観測の進展に伴い,飛躍的な発展を遂げてきた.特にこの20数年の間に,遠方のIa型超新星サーベイ,探査機WMAPやPlanckに代表される宇宙マイクロ波背景放射の精密観測,それにスローン・デジタル・スカイサーベイなどの大規模銀河サーベイから続々と観測結果が報告され,宇宙の膨張と構造の進化を統一的に記述する「標準モデル」が確立したことは,大きな成果である.その華々しさは,2000年代に3度のノーベル物理学賞,6名もの受賞者を輩出したことからも窺える.なお「標準モデル」の確立には,日本人研究者の多大な貢献があったことも忘れてはならない. そのような現代宇宙論に関心を寄せる人は,数多くいることだろう.最近では,宇宙に関するニュース・話題はネットなどでも頻繁に見かけるようになっており,分野を問わず,年齢を問わず,幅広い層からの関心があるかもしれない.
言うまでもなく,現代宇宙論は,物理学をベースにした学問分野である.扱う対象は,宇宙そのものと,そこに存在する銀河・銀河団などから成る巨大な構造(大規模構造と呼ばれる)の時間進化である.ミクロからマクロまで,様々なスケールで現れる物理現象を記述するため,素粒子物理,量子力学から熱・統計力学,電磁気学,流体力学など,様々な物理学が総動員される.中でも,一般相対性理論は,宇宙の進化に圧倒的な影響をおよぼす重力場を記述する理論として,最も本質的である.そのため,宇宙論をしっかりと学ぶには,物理基礎教科を一通り学び,さらに一般相対性理論の知識を踏まえてからが望まれる.つまり,物理学科の学生でも学部4年生か,大学院生以上からの習得が適当である.
本書は,習得までに時間のかかる一般相対性理論の前提知識なしに,現代宇宙論が学べるようにと,意欲ある学生へ向けた「入門」書である.ソフトカバーA5版で本文235ページと,コンパクトなサイズでまとめられた本書ではあるが,全9章,理論から最近の観測結果までかなり「がっつり」と書かれている.おおまかには,宇宙膨張と物質進化の歴史についての記述と(第1~5章),物質・輻射のゆらぎ(空間非一様性)についての説明にわかれ(第6~8章),最終章9章は暗黒エネルギーの解説に割かれている.なお,本書の著者はインフレーションや暗黒エネルギーの専門家でもあり,その意味でも第9章は本書の特色といえそうだ.全体を通して随所に一般相対性理論が必要になる内容ばかりだが,第2章では,ニュートン力学における一様球の運動のアナロジーをベースに,熱力学の法則とも絡めながら,膨張宇宙モデルの基礎方程式であるフリードマン方程式を「導出」している.その他の章でも一般相対性理論の重要性をちらつかせながらも,複雑さを避けて物理的本質に焦点をあてた解説が試みられている.ただし,宇宙マイクロ波背景放射の記述がある第7.3章では,摂動がある宇宙での測地線方程式を用いて,光の伝搬過程を通じて現れる相対論的効果を説明するくだりがあり,さすがに一般相対性理論の知識が必要になる.とはいえ,結果の物理的意味は明確なので,細部に拘りさえしなければ読み進めていけそうだ.その意味で,一般相対性理論の知識を前提としないという,本書の目標は概ね達成されたといえるかもしれない.
とはいえ,本書は,物理基礎教科の知識を大前提としている点を,十分,心にとどめて読み進めるべきである.ある程度自己完結的な記述が試みられてはいるが,少なくとも解析力学,熱・統計力学,量子力学,それに流体力学あたりの基礎を習熟していないと,それらを総動員して得られる新しい知見や概念の理解には追いつかないだろう(本書に限った話ではない).また,やはり一般相対性理論の知識なしに正確な理解は得られないし,誤解が生じうる.著者自らも勧めているように,本書の付録や他の宇宙論の教科書を参照しつつ,理解を深めるべきである.加えて本書は,最新の観測成果を紹介しながら,現代宇宙論の成り立ちを説明しているため,その情報量は圧倒的である.全くの初学者が,溢れる情報を整理しつつ,宇宙論の概念などをおさえるにはかなり手強そうにも思える.そういう意味では,本書は入門書というより,現代宇宙論を俯瞰するための情報をコンパクトな1冊にまとめたハンドブックともみなせそうだ.学生向きというより,大学院生・専門家にむしろ有用かもしれない.
最後に,観測に関する説明について気になる点が散見されたので,気づいたものを挙げておく.1つは,宇宙論における距離の説明である.宇宙論的な距離が宇宙モデルにどう依存するかが後半まで読み進めないとわからないし,与えられた関係式は,平坦な宇宙に限られ,閉じた・開いた宇宙では適用できないため,注意を要する.2つめは,第8.5章のバリオン音響振動を用いた宇宙論的な距離の測定方法に関する説明が不正確な点である.特に,(8.91)式あたりの記述は正しくない.また(8.92)式は,1次元相関関数ではなく1次元相関関数から求まるシフトパラメータの誤りである.その他,第7.8章の宇宙マイクロ波背景放射の偏光に関する記述や,第9.2章のIa型超新星観測から距離を決める方法についても,記述が端折られていて誤解や間違った印象を与えそうに思えた.これらの間違い・誤植等は,第2版に訂正・改善されていれば幸いである.
(2023年7月17日原稿受付)
グラフェンの物理学;ディラック電子とトポロジカル物性の基礎
越野幹人 著
内田老鶴圃,東京,2023,x+232p,21 cm×15 cm,4,400円(物質・材料テキストシリーズ)[専門・大学院向]ISBN 978-4-7536-2321-1
紹介者:磯部大樹〈理研創発物性科学研セ〉
グラフェンは炭素原子が蜂の巣格子を組むことにより構成される原子1つ分の厚さをもつ物質である.炭素原子が共有結合することによりできるこの物質は,それ自体が興味深い機械的・熱的性質を示すと同時に,原子単層の厚さの理想的な2次元電子系である.1947年にWallaceにより低エネルギー有効模型が相対論的なDirac電子系となることが示されていたが,その後2004年にGeimやNovoselovらにより粘着テープを用いた剥離でグラファイトから単層グラフェンを作成できることが報告されたことを契機に,実験と理論の両面において研究が大きく進展した.近年では2018年にCaoやJarillo-Herreroらにより単層グラフェン2層をわずかにずらして積層させたねじれ2層グラフェンにおいて,電子相関効果により絶縁体や超伝導体に転移することが実験的に示され話題となっている.本書の表紙イラストにもなっているねじれ2層グラフェンは,最近の物性研究のハイライトのひとつといえる.
本書はグラフェンに関する多くの論文を記した著者による,最新の研究の進展を含むグラフェンおよびその他の2次元物質に関連する事項を網羅する教科書である.2次元電子系としてのグラフェンは物性研究のあらゆるトピックと関連する興味深い物質であるが,それは同時に研究を行うにあたり広範な知識を必要とすることを示唆する.本書ではDirac電子系やトポロジカルな性質を中心に,最近のねじれ2層グラフェンを含む最前線の研究を理解するために必要な事項が理論研究者の観点から簡潔にまとめられている.グラフェンに関する研究の動向のフォローを目的とする研究者や,これからグラフェンや2次元物質に関する研究を始めようとする大学院生を対象として,この分野を俯瞰し,より基礎的な教科書と最近の論文との間をつなぐ橋渡しとなる教科書である.
目次から分かるように本書の網羅する内容は多岐にわたり,なによりグラフェンに関する物理の広がりを物語る.まずグラフェンの発見と関連する2次元物質の解説(第1章)から本書は始まる.続いて固体物理の基礎を振り返りつつグラフェンを特徴付ける性質のひとつであるDirac電子系としての性質を強束縛模型から導出し,乱れの効果などを踏まえて電気伝導や光学応答に関する説明がなされる(第2,3章).グラフェンの持つ別の側面としてDirac電子系に端を発するトポロジカルな性質があるが,強磁場下におけるLandau準位と量子Hall効果の説明を経てBerry位相が導入される(第4,5章).波数空間で記述され抽象的にも見えるBerry接続やBerry曲率であるが,本書で示されるようにWannier軌道や異常速度を通してその一端を理解できる.トポロジカルな性質の発現についてはグラフェンナノリボンにおけるエッジ状態を用いて例示される.関連するトポロジカル格子模型(第6章),すなわち種々の質量のあるDirac模型(第7章)についても紹介されている.グラフェンはグラファイトを剥離して作成できることから分かるように,層間結合は弱いvan der Waals結合によるものである.これがグラフェンの物質設計における自由度を高めている主因であり,多層グラフェンにおける積層パターンの効果についてトポロジカルな性質との関連を踏まえて解説される(第8章).
第9章のモアレ2次元物質に関する記述は本書の到着点といえよう.モアレ2次元物質は,2次元物質を積層させて作るvan der Waals物質のうち,単層グラフェン2枚や,グラフェンと六方晶窒化ホウ素の組み合わせなど,各層の格子定数が同じかごく近い場合に全体の格子構造に長周期のモアレ模様が現れる物質系である.近年の物性研究の一大テーマであり,シンプルにも見える物質系だが背景や発現する物性には物性物理学のさまざまな事柄が関連しており,8章までの内容はモアレ2次元物質のための準備を整えたとみることもできる.グラフェンについてすでに詳しく,モアレ2次元物質の基礎について知りたい読者はこの章をまず読むことも可能であろう.単層グラフェンは非常に速いFermi速度(~106 m/s)を示すが,2011年にBistritzerとMacDonaldによりねじれ2層グラフェンでは長周期モアレ構造に伴い,2層の相対角度に応じて非常に平坦なエネルギーバンドが形成されることが理論的に示された.この平坦なバンド構造が実験でも確認された電子相関効果の増大と関連するが,実際にはモアレ構造に伴う格子緩和が電子状態にも多大な影響を与えるなど注意が必要である.著者はモアレ2次元物質のエネルギーバンド計算にも多大な貢献があり,本書を通じてその要点・機微を直接学ぶことができる.
このように本書ではグラフェンにまつわるさまざまなトピックが理論研究者の観点からまとめられており,簡潔ながらも詳細まで配慮した記述が見られる.一方で,物質の合成や実験,また応用などについても随所で触れてあり,グラフェンの物理学について気負うことなく知識を深めることができる.さらに数式の記述についても工夫が成されており,自ら導出を行うことでより理解を深めることができるだろう.
(2023年7月24日原稿受付)
微生物流体力学;生き物の動き・形・流れを探る
石本健太 著
サイエンス社,東京,2022,iv+201p,21 cm×15 cm,2,970円(ライブラリ数理科学のための数学とその展開-AP1)[大学院向]ISBN 978-4-7819-1559-3
紹介者:内田就也〈東北大院理〉
バクテリアやゾウリムシなどの微生物の遊泳は,生物の運動の中では数理的な解析が最も進んでいる問題の一つである.この分野は,1951年のG. I. Taylorの仕事を嚆矢として長い伝統を持つが,近年,アクティブマターと総称される非平衡系の研究の進展に伴い,新たな脚光を浴びている.本書は,微生物の流体力学をその基本から最近の研究成果に至るまでまとめた,邦書としては他に例を見ない教科書である.
第1章では,遊泳する微生物の分類や,鞭毛や繊毛とよばれる運動器官の概要が紹介された後,微生物の世界の特徴的なスケールが示される.第2章では,流体力学の基礎方程式であるナビエ-ストークス方程式に続いて,その慣性項を無視した近似であるストークス方程式の基本的性質が述べられる.第3章では,剛体の流体抵抗が定式化された後,体を変形させて遊泳する物体の理論が展開される.特に重要な結果は,ストークス方程式の時間反転対称性に起因するパーセルの帆立貝定理である.これは,帆立貝の貝殻の開閉のような,形状空間において同じ経路を往復する運動では,正味の移動が生じないことを示した定理である.したがって,微生物が遊泳するためには単純な往復運動ではなく,回転的な運動を用いる必要があることが分かる.第4章では,遊泳する物体の周りの流れ場の構造が議論される.流れ場は多重極展開で表され,その基本的なパターンは,力の二重極(双極子)の構造によって分類される.また,数値計算に必要となる理論的枠組みもこの章で解説されている.第5章は,個体と流れの相互作用,および個体間の流れを介した相互作用の解説にあてられている.実際の例としては,精子が流れに逆らって泳ぐ性質,境界壁に近づく性質,他の精子と協調して泳ぐ性質などが挙げられている.第6章では,微生物の集団の性質に焦点が当てられる.章の前半では拡散やレオロジーについて述べられた後,後半ではアクティブ乱流や生物対流など,巨視的スケールで生じる集団運動が紹介されている.アクティブ乱流は微生物に限らず自己駆動性を持つ粒子の集団で普遍的に見られる現象である.一方,生物対流は,微生物が重力や光を検知して移動する性質に起因する.第7章では,より複雑な問題として,微生物の体の曲げ弾性や表面張力による変形が関わる現象や,流体の慣性の効果が取り上げられる.最後に,遊泳効率の最適化の問題が,生物の行動・生態・進化のメカニズムの力学的理解という未解明の問題の一つとして掲げられている.
本書は,定理,命題,証明といった数学書の体裁を取りつつも,多くの図が挿入されていることでイメージが湧きやすく,実際の微生物への応用が豊富な例によって解説されているため,物理を専攻とする学生にも楽しく読み進められる教科書となっている.また,より専門的な理解へのガイドとしては,本文中に挿入された注や,多数の参考文献への誘導が役に立つ.内容的にも年代的にも広範にわたる生物流体力学の諸結果が,見通しよく整理され,日本語で学べるようになったことの意義は大きい.生物物理やアクティブマター,および応用力学一般に関心を持つ多くの方に一読をお勧めしたい.
(2023年9月4日原稿受付)
科学と仮説
科学と仮説
アンリ・ポアンカレ 著,南條郁子 訳
アンリ・ポアンカレ 著,伊藤邦武 訳
筑摩書房,東京,2022,336p,15 cm×11 cm,1,210円(ちくま学芸文庫)[一般向]ISBN 978-4-480-51091-4
岩波書店,東京,2021,494p,15 cm×11 cm,1,320円(岩波文庫 青902-1)[一般向]ISBN 978-4-00-339029-0
紹介者:高橋 浩〈群馬大理工〉
原著は1902年出版であり「新著紹介」に相応しくないが,最近,新訳が2つ相次いで出版されたので紹介したい. 「仮説」の役割を中心にしてポアンカレ自身の科学思想を一般読者向けに語った原著は,本国フランスでベストセラーになり,直ちに,英語やドイツ語に翻訳され多くの読者を獲得した.日本語訳も林鶴一によって『科学と臆説』の題名で1909年にはもう出版されている.アインシュタインも1904年に出版されたドイツ語訳をその年に熟読したらしい.南條訳の解説(南條訳p. 304)でも指摘されているように「相異なる舞台で起こる二つの事象の同時性について直接的直観さえ持っていない」(南條訳(第6章p. 121))や,「この特異な運動(注:ブラウン運動)はカルノーの原理に従っていない」(伊藤訳(第10章p. 305))などといった記述は,大いに彼を刺激したであろう.
2つの新訳を比較しての全体的な印象は次の通りである.これまでも多くの数学啓蒙書の翻訳を手掛けてきた南條氏の訳の方が,日本語としてこなれていて読みやすい.伊藤氏のものは,ポアンカレの考えを誤解なく読者に伝えることを大切にしていることが,ひしひしと伝わってくる訳文である.そのために全体的に文章が長く,ややくどい感じになっている.エネルギー保存則に関連して登場する文を例に比較してみる.南條訳は,「もし世界が法則によって支配されているならば,一定に保たれる量が存在することは明らかだ」(南條訳(第8章p. 162))であり,一方,伊藤訳では,「世界がもろもろの法則によって支配されているのであれば,定数にとどまるようないくつかの量が存在するであろうことは明白である」(伊藤訳(第8章p. 228))となっている.伊藤氏の単数,複数の差を明確にする姿勢は,高く評価したい.
新訳登場以前親しまれていた岩波文庫の河野伊三郎訳(1938年初版,1959年改訂)と比較すると,河野訳で,「ケプレル」「エネルギー恒存の原理」(索引参照)と表記されているものは,新訳はどちらも「ケプラー」「エネルギー保存(の)原理」(索引参照)と現代的な用語になっている.原著の"la philosophie naturelle"を,河野訳では「自然科学」(改訂版p. 157)としているが,2つの新訳はともに,そこは敢えて「自然哲学」(南條訳p. 164,伊藤訳p. 230)としているのは興味深い.第10章に登場する小見出"La physique et le mécanisme"は,河野訳では,「物理学と力学観」(改訂版p. 196),伊藤訳では,「物理学と力学的世界観」(p. 287),南條訳では,「物理学と力学理論」(p. 206)と3者で異なっている.訳者の個性,考え方が反映した部分であろう.
伊藤氏の訳に関して1点だけ,紹介者が戸惑った部分があった.それは,確率計算に関係して登場する"instinct"という言葉に対しての訳し分けである.ポアンカレは,全体の要約を序文として掲載している.序文でも確率計算の議論の部分に"instinct"という言葉が登場する.南條訳は,序文,本文第11章の両方で「直感」(p. 13, p. 227)という言葉で統一している.因みに,旧訳の河野氏のものでも,序文では「感じ」(p. 18),本文では「直感」(p. 216)としていて,ほぼ同じ訳語になっている.一方,伊藤訳は,序文では「本能」(p. 11)とし,本文では「直感」(p. 315)としている.「本能」と「直感」ではだいぶ印象が違う.哲学者である伊藤氏には,何か深い意図があるのかもしれないが,紹介者にその訳し分けの意図がくみ取れなかった. 巻末解説と原著にはない索引の存在は,両新訳書の価値を高めている.巻末解説のスタンスは,両者で大きく異なっている.伊藤氏の解説は,『科学と価値』などのポアンカレの他の著作にも言及しながら,彼の科学哲学思想を要約し,その一貫性とある種の保守性を指摘している.一方,南條氏は,『科学と仮説』を解釈する際,前提となるカント哲学について解説している.紹介者のように哲学に疎い読者にとっては大変にありがたい.索引に関しては,両者ともにやや不満がある.伊藤訳書の索引には,「一様性」「時間」「矛盾律」という項目はあるが,南條訳書には登場しない.逆に,南條訳書の索引には,「帰納」「科学」「変位電流」は登場するが,伊藤訳書にはない.人名解説が伊藤訳書にあるが,その人物への言及が何ページでなされているかの索引はない.一方,南條訳書には,人名による索引が完備されている.
科学哲学,科学史の専門家は原文を読むであろうが,一般の物理学徒や物理学者にとって,この古典の現代日本語訳が2つも同時に登場したことは大変に喜ばしいことである.是非2冊とも入手し,読み比べることをお勧めする.
新訳2種類が,ほぼ同時に出たのは偶然であろうか.もしかすると,科学における探究だけでなく現代社会一般においても,「仮説」の役割が今注目されているためかもしれない.従来の「総合的な学習の時間」に代わって,2022年度から高校必履修科目として登場した「総合的な探究の時間」について『高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説』*1では,社会や地域の問題に対して「その解決に向けて仮説を立てたり,調査して得た情報を基に分析」(第7章p. 84,傍点:紹介者)することを各校の設定目標の例として挙げている.『解説』は学習指導要領の改訂の度に発行され,現場に強い影響力を持っている.
*1 https://www.mext.go.jp/content/1407196_21_1_1_2.pdf
(2023年11月7日原稿受付)